言わずと知れたお茶の時間、ロザリアは地の執務室にいた。
「ルヴァ。」
「はい~~?」
気のない返事にイラッとして、ロザリアは少し大きな声を出してみた。
「ルヴァ。お茶ですわ。」
「はいはい~~~?」
返事だけで、視線を動かそうともしない態度に、ロザリアはわざと湯呑を反対側に動かしてみる。
すると、ルヴァはいつも湯呑の置かれているあたりに、手だけを動かして探っていた。
「ルヴァ!」
「はい?!」
突然大声に今度こそルヴァが顔をあげた。
目の前のロザリアの顔と、反対側に置かれた湯呑を交互に見て、申し訳なさそうな苦笑いを浮かべている。
「すみませんねぇ。・・・えーっと、なにか御用ですか?」
相変わらず、手は本のページを押さえたまま。いつでも続きを読めるようにしているのは明白だ。
ロザリアはルヴァの悪びれない様子に肩を落とした。
「お茶の時間ですわ。わたくしもご一緒してよろしいかしら?」
「はい、どうぞ。お菓子でしたら、そこにありますからね~。」
ルヴァは再び本に視線を戻すと、ロザリアの淹れたお茶をすすりながらページをめくった。
窓の外は、常春の聖地らしい見事な晴天で、遠くに小鳥のさえずりが聞こえてくる。
大きな窓から差し込む午後の日差しはとても柔らかで、ポカポカとして暖かな空気のなか、のんびり本を読む幸せをルヴァは満喫していた。
これ以上はないだろう至福の時間。
そんなルヴァの幸せそうな顔に、ロザリアも小さく微笑むと、そばのソファに腰を下ろした。
手には1冊の本。
二人は午後のお茶の時間をそれぞれに本を読みながら過ごしていたのだった。
「まーるで、お年寄りみたいね。」
アンジェリークは唖然として、ロザリアをまじまじと見つめた。
毎日、ルヴァの執務室でお茶の時間を過ごしているのだから、さぞかしお熱いのだろうと期待をしていたのに。
「でも、楽しいんですの。わたくしがよければ、何の問題もありませんでしょう?」
「それはそうだけど…。ね、じゃあ、ルヴァはなんて告白してきたの?『あ~、その~。』とか長くかかったんでしょ?」
「告白?」
ロザリアの瞳に微妙な色が浮かぶのを、アンジェリークは見逃さなかった。
「え!まさか、あなたたち、まだ、付き合ってないの?!」
「アンジェ!声が大きいですわ!」
つい名前で呼んでしまったロザリアは、じろりとアンジェリークを睨みつけると、ここからは友達の時間、とでもいうようにペンを置いて、指を組んだ。
「ええ。まだ、特別なことはなにもありませんの。ただお茶の時間、一緒に本を読んでいるだけですわ。…追い返されたことはありませんから、嫌われてはいないと思うのですけれど。」
困ったような、嬉しいような、なんとも言えない微妙な表情のロザリアにアンジェリークは内心おかしくてたまらない。
どう考えても、二人が両想いなのはわかりきっていて。
でも、当の本人は全然気付いていないのだから。
「たしかにルヴァはあの通りのぼんやりさんだから、自分から告白なんてしそうもないかも。」
アンジェリークがちょっと考えながら、頷いてみせると、ロザリアは不安そうな顔をしている。
わざと大げさにぽんと手を叩いてから、ロザリアの肩に手を置いた。
「そうだ!いっそロザリアから言ってみたらどう?」
「わたくしから?」
「ホラ、もうすぐバレンタインデーでしょ?本命チョコレートを渡したら、さすがのルヴァでも気づくんじゃないかな?」
「バレンタインデー・・・。」
卓上カレンダーをちらりと見れば、たしかにバレンタインデーは目の前だ。
毎年、義理チョコを二人で配って来たけれど。
「ね、今年のバレンタインは配るだけじゃなくて、特別な日にしよう!スペシャルチョコ、一緒に作ろう?」
実は一人でチョコを作るのが不安だったアンジェリークは、ここぞとばかりに畳みかけた。
お菓子作りの得意なロザリアと一緒に作れば、安心だ。
そんなアンジェリークの心の叫びが届いたのか、ロザリアは小さく頷いた。
そろそろはっきりしたいという思いもたしかに心の中にある。
「ええ。わたくしも特別な日にしてみますわ。」
「うん!がんばろうね!」
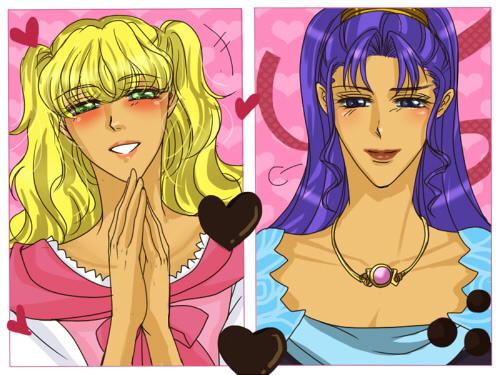
なぜか大喜びで首にかじりついてきたアンジェリークの背中をよしよしとさすりながら、ロザリアは心臓が踊りだすのを感じていた。
受け入れられるにしろ、フラれるにしろ、想いに答えが出ることは間違いない。
こうして、ロザリアは特別な日のスペシャルチョコを作る事になったのだった。
当日。
バレンタインの日はどこもかしこもそわそわと浮かれていた。
前日にアンジェリークと作ったチョコは今、ロザリアの手の中にある。
両手のひらにちょうどおさまるくらいのピンクの箱に、大きな白いオーガンジーのリボン。
リボンの真ん中に挿した薔薇は今朝、庭に咲いていた一番綺麗な薔薇を摘んできたものだ。
お茶の時間までしおれないように、一輪ざしに挿しておいた薔薇は今も生き生きとロザリアを応援してくれているように見える。
いわゆる義理チョコは午前中のうちにアンジェリークと配っておいたから、これが本当に最後の一つ。
いつもよりも早すぎないように、と思いながら、いてもたってもいられなくて、ロザリアはもう10分も地の執務室のドアの前に立っていた。
何度も繰り返した深呼吸のあと、ようやくドアをノックすると、ルヴァののんびりした声がする。
ロザリアはカチコチになった棒のような足をなんとか動かして、中へと入って行った。
おそるおそる入っても、ルヴァは本を読んでいて、顔をあげることはしない。
それはいつものことで、このあと、ロザリアは黙ってお茶を淹れに奥へ行くのだが、今日はお茶のことに頭が回らない。
ロザリアはまっすぐルヴァのそばへ向かった。
「あの、ルヴァ。」
「はい~。」
相変わらず目線は本のまま。
ロザリアは息を吸い込んだ。
「あの、ルヴァ。今日はルヴァにお渡ししたいものがありますの。」
「渡したいもの?なんですか?」
ルヴァはようやく顔をあげたが、本はまだ開いたままで、いつでも続きが読み出せるように手がページを抑えている。
「これですの。」
綺麗な箱に一瞬驚いたような顔をしたルヴァは、すぐに微笑んだ。
「ずいぶん立派ですねぇ。中身はなんですか?」
言葉に詰まったロザリアだったが、「チョコレートですわ。」と、なんとか一言絞り出した。
「チョコレートですか。なんだか開けるのがもったいないですねぇ。今度いただきましょうか。」
あんまりにいつも通りの調子でそう言われたロザリアは、つい頷きそうになって、慌てて、箱を開いた本の上に置いた。
「いいえ。今日、今、開けていただきたいんですの。すぐに食べていただかないと味が落ちてしまいますのよ。」
「ですが・・・。」
「いいえ、今すぐにお食べになってくださいませ。」
別にそれほど急ぐ必要はないのに、なぜかロザリアはムキになってしまっていた。
ひょっとして、ルヴァはバレンタインデーだと気付いていないのかもしれない。
あまりにいつも通りの態度が、逆にロザリアの平常心を奪っていた。
「では、開けてください。」
ちょっと気圧されたようなルヴァがそう言うと、ロザリアは首を振った。
「ルヴァが開けてください。差し上げたものを開けるなんて、礼儀に反しますわ。」
「いえ~。こんな綺麗な包装をきちんと開ける自信がないんですよ~。せめてリボンだけでもほどいていただけませんかね~。」
仕方なくロザリアは大きな薔薇を机の隅に置いて、リボンだけをほどくと、ルヴァに箱を手渡した。
「ありがとうございます~。では。」
ルヴァがゆっくりとペーパーを外すと、中からキラキラしたピンクの箱が現れた。
アンジェリークに薦められて選んだ色だが、なんとなく自分らしくないようで、ロザリアは恥ずかしい気がする。
蓋を開けると、箱の中にはミルクとホワイトの2種類が市松に並んだ丸いトリュフが4つ。

ルヴァはじっとトリュフを眺めた後、嬉しそうに笑顔になった。
「ああ~、おいしそうですねぇ。あとで、きちんといただきますから。」
蓋を箱に重ねて、中身が見えるようにしたまま、ルヴァはトリュフを机の隅に置くと、再び本に視線を落とした。
部屋の中に香る、チョコレートの匂い。
「ルヴァ。今すぐと言いましたわ。後でではなくて、今すぐ食べて欲しいんですの。」
「はい?」
ロザリアの声にルヴァはびっくりして、顔をあげる。
けれど、まだ、開いたままの本にロザリアの中でなにかがキレた。
「お食べくださいませ!今すぐに!」
机の隅に置かれた箱を再びルヴァの目の前に付き出した。
ルヴァが困ったような顔をしていたが、今はそれどころではない。
「早く。」
ロザリアは本の上に箱を置いた。
「ですが・・・。手が汚れます。」
「え?」
ルヴァの言葉にロザリアは耳を疑った。
「このチョコレートは回りに粉がたくさん付いているじゃありませんか。手が汚れると、本が読めません。」
「本が…。」
なんだか悲しいのと、腹立たしいので、ロザリアは目眩がしそうだった。
結局のところ、ルヴァは本が大切なのだ。
チョコレートよりも、自分のお願いよりも、なによりも。
ロザリアが箱からチョコレートをつまむと、回りについていた粉がはらはらと本の上にこぼれていく。
「ああー!!ロザリア!チョコレートが!」
慌ててルヴァは本を取り上げると、ページを手で懸命に払う。
うっすらと茶色がしみ込んでしまったのを見て、ため息をついた。
「ロザリア。こんな貴重な本を汚すようなことをするなんて、どうしたんですか?貴女らしくありませんよ~。」
「どうした、ですって?」
本当に困ったような顔をしているルヴァに、ロザリアの肩から力が抜けた。
もう、限界。これ以上は、自分がみじめになるだけだ。
「いいえ。なんでもありませんわ。もう、いいんです。」
「はい~?」
涙が出そうになるのをぐっとこらえて、ロザリアは箱を手に取ると、元通りに蓋をした。
「申し訳ありませんでしたわ。失礼します。」
ロザリアはいつも通りににっこりと微笑むと、箱と薔薇を手に部屋を出ていった。
ぽつんと取り残されたルヴァ。
しばらくして、目が覚めたように本を机に置こうとして、チョコの粉がこぼれているのに気付いた。
「一体…。どうしたんでしょうか?」
ティッシュでチョコを掃除しようとしたとき、ドアに隙間があいた。
隙間からこぼれる、ふわふわとした金の髪。
「ルヴァ。チョコの味はどうだった?」
「陛下?なぜチョコレートのことを知っているんですか?」
逆に質問されたアンジェリークは唇をとがらせながら、中に滑り込んできた。
「知ってるもなにも…。だって、一緒に作ったんだもの。おいしかったでしょ?ロザリアってば何でも上手なのよねー。」
なんだかうっとりしているアンジェリークを横目に、ルヴァはティッシュで机の上を拭いた。
チョコ色になるティッシュにふと、疑問がわく。
「なぜ、チョコレートなんですか?」
「え?!・・・まさか。」
きょとんとしたアンジェリークの瞳がだんだんとぎょっとした様子に変わる。
ルヴァは首をかしげながら、ゴミ箱にティッシュを捨てた。
「今日が、バレンタインデーって、知ってるわよね…?」
「え?・・・・ええーーーっ!!」
ルヴァの叫び声と、アンジェリークのため息が盛大に重なった。
「すっかり忘れていました…。」
見るからに萎れてしまったルヴァが、ふと思いついたようにアンジェリークを見つめる。
「あの、それでは、もしかして、ロザリアは、その・・・・。」
アンジェリークは人差し指をずいっとルヴァに突き出すと、まっすぐに睨みつけた。
「ねえ、ルヴァ、もしかして、なんかとんでもないことしちゃったんじゃないの?」
ルヴァの背中に冷たい汗のようなモノが流れる。
それがお茶の時間を過ぎて、日差しが翳って来たせいだけではないことは、自分でもよくわかっていた。
「あ、あの、私はどうしたら・・・。」
「しらないっ。」
アンジェリークは急にぷいっとそっぽを向くと、両手を腰にあてた。
ロザリアが怒っている時によくそのポーズをする、とルヴァはぼんやりと思う。
「お返しならホワイトデーがあるけど、チョコを貰ってもいない人がどうするかなんて、わたしは知らないわよーだ。」
「ホワイトデーですか…。」
たしかちょうど1カ月後。チョコを貰った男子が好きな女子にお返しを送る日。
考え込んだルヴァをアンジェリークが見下ろした。
「ホントに知らないんだから。」
足音も高くアンジェリークが出ていったあとも、ルヴァはただぼんやりと座り込んでいた。
お茶の時間はとうに過ぎ、なんだかとても喉が渇いている。
だけど。
いつも湯呑が置かれている場所にはただ窓から伸びるオレンジ色の光だけが眩しく輝いていた。
あの日から、聖地では2度、雨が降った。
その間、ロザリアは一度も地の執務室に行っていない。
お茶の時間が来て、ロザリアは二人分の紅茶を淹れると、アンジェリークの前にカップを置いた。
「ねえ、ロザリア。今日もここなの?」
ふうふうとカップに息を吹きかけながら、アンジェリークが尋ねると、ロザリアは眉を寄せて頷いた。
「邪魔なら出ていきますわよ。…どうやらあの方がいらしたようですし。」
ロザリアは自分のために淹れた紅茶のカップをアンジェリークの隣に並べると、席を立った。
入れ替わりに女王の間に入って行く人影を見て、思わずため息が漏れる。
ロザリアは仕方なく、中庭に向かった。
ルヴァの手元で本のページがかさかさと音を立てている。
気分転換にと、開け放った窓から流れてくる優しい風が背中をなでると、机の上をかすめていった。
何度も時計を見上げては、漏れてくるため息。
お昼を過ぎて、かちかちとまるで時限爆弾のように時が刻まれていき、やがて夜が来てしまう。・・・一度も彼女の姿を見ないまま。
あれほど読みたかったはずの本が目の前にあるのに、少しも頭に入らない。
少し読んでは、内容がわからなくなって、また数ページ戻る。
そんなことを繰り返していた。
お茶も自分で淹れてはみるものの、本当に同じ茶葉なのかと思うほど味気ない。
「なぜでしょうねぇ。」
ルヴァにだって本当はわかっている。
そこにロザリアがいないというだけで、お茶は味がなく、本は文字の羅列になってしまっているということ。
今も書いてある解説がわからなくて、ルヴァは前へとページをめくった。
だいぶ前に書かれていた説明文がどうやら全く頭に入っていなかったらしい。
パラパラとページをめくったルヴァの手が止まる。
ページの隅に、綴じしろに、点々と散らばる茶色の染み。
あの日、チョコレートが付いてしまったページ。
「私は…なにをしてしまったんでしょうか。」
ロザリアがいてくれて、微笑んでいてくれて、それが当たり前のことのようになっていて。
彼女が淹れてくれるお茶の味や、ふと香る薔薇の香りが、どれほど心を暖かくしてくれていたのか、すっかりわからなくなっていて。
ロザリアがいなければ、本を読むことさえ集中できないのに。
ルヴァは本の上に手を置いて、窓の外を見た。
すぐそばに立つ大きな木の向こうの中庭に、人影がある。
見慣れたはずの姿なのに、今まで見たどの彼女よりも胸がときめいた。
思わず椅子を蹴って立ち上がったルヴァは、2、3歩歩いて、また元の椅子にどさりと腰を下ろす。
「今さら、遅いでしょうね…。」
大きな木が風に揺れて、葉を透かした光も一緒に揺れる。

中庭のベンチに座って本を読むロザリアの長い髪も風に流れていた。
綺麗で、胸が痛い。
ルヴァが再び大きなため息をつくと、背後から足音が聞こえてきた。
「ちょっと!これであきらめちゃうの?!」
「陛下!どうしたんですか?!」
勢いよく開いたドアから床を蹴破るように入って来たアンジェリークはどんどんルヴァに近づくと、執務机に両手をついた。
「ルヴァはそれでいいの?本当にロザリアとこのまま気まずくなって、それでいいの?」
「いえ・・・。私は…。」
「なに?!」
じろり、と睨みつけられてルヴァは肩をすくめた。
「ただ、その、もうバレンタインデーは終わってしまったし、なんていうか、ああ、ホワイトデーまで待った方がいいのかな~なんて、思っただけで…。」
「え?!ホワイトデー?!まだまだ先じゃない?」
「ですけれど、なんでもない日にね、その、なにかあるよりは、特別な日にあった方がロザリアも喜ぶのではないかと…。」
ウソではない。
きっかけが欲しいのだ。特別なことをする日、たとえばホワイトデーのような日なら勇気を出せるような気がする。
「ルヴァ。」
アンジェリークの声はとても落ち着いていて、ルヴァは身を固くした。
「それは違うと思うの。バレンタインデーだって、別に特別な日じゃないわ。」
緑の瞳がにっこりと微笑む。
「大好きな人にチョコレートをプレゼントしたり、告白したりするから、その日が特別な日になるだけよ。」
「だから、今日だって、ロザリアにとって特別な日になれると思うの。女の子にとって好きな人から告白されるなんて、そんな素敵な日は絶対に『特別』だから。」
開いたままだった本のページがパラパラとめくれていく。
チョコレートの付いたページもどこかに隠れて見えなくなった。
「あの~。陛下。ちょっと席をはずしてもいいですかねえ。」
立ち上がったルヴァの顔にあたる西日に、木の葉の影が揺れる。
アンジェリークが返事をする前に、ルヴァは走り出した。
「あら、ルヴァったら、結構走るの速いのね。」
覗き込んだ窓から中庭を走るルヴァの姿が見えると、アンジェリークはふふっと微笑んだのだった。





時計の針はもうすぐ3時。
かちっと長針が12を指すと、同時にノックの音がする。
ルヴァは本を閉じて立ち上がり、部屋のドアを開けた。
「お茶をご一緒してもよろしいかしら?」
頬をほんのりと染めたロザリアは、ルヴァに促されて部屋に入ると、奥へ向かう。
そわそわと執務机に座ったルヴァは漂って来るお茶の香りを吸い込むと、トレーを持ったロザリアが湯呑を置くのを見つめた。
「ありがとうございます~。」
一口お茶をのんで、いつもの場所に湯呑を置く。
さっき閉じた本を元通りに開くと、すぐそばのソファにロザリアも腰を下ろした。
大きな窓から差し込む、やさしい光。
ポカポカとした陽気に包まれてしばらく二人で本を読んでいると、ロザリアが持っていた袋から箱を取りだした。
「これ、お食べになりませんか?」
キラキラのピンクの箱に入っていたのは、ミルクとホワイトの丸いトリュフ。
「作り直しましたの。ルヴァに食べていただきたくて。」
ロザリアが机の隅にそっと箱を置くと、甘いチョコレートの香りが辺りに広がった。
あの日、食べそこなったチョコレート。
ルヴァは本を閉じると、すぐに手を伸ばした。
「お待ちになって。手が汚れますわ。」
「いいんですよ。私が今、食べたいんですから。」
チョコをつまもうとした瞬間、ロザリアは箱をさっと自分の方に取り上げた。
「ロザリア?」
思わず見つめたルヴァの目の前で、ロザリアの白い手がトリュフをつまむ。
「ホワイトでよろしいかしら?」
「はい?」
「口を開けてくださいませ。それでは食べられませんでしょう?」
「・・・はい。」
ルヴァの口の中に白いトリュフが転がる。
その甘い甘い味は、中庭で彼女を抱きしめた時に感じた気持ちによく似ていた。
「これなら、手も汚れませんわ。」
微笑んだロザリアに、ルヴァも微笑み返した。
「いいえ。やっぱり汚れると思いますよ~?」
ルヴァはミルクのトリュフをつまむと、ロザリアの口元へ寄せた。
「はい、貴女もどうぞ。」
バレンタインデーが特別なチョコレートを食べる日だとしたら。
きっと今日が、二人にとってのバレンタイン。

FIN
