ざらざらとした固い葉脈と、剣のように鋭い形。
昼間は汗ばむほどなのに、この時間になると頬を撫でる風は涼やかで。
その風に揺れる葉も、さらさらと穏やかな音を立てている。
大広間のバルコニーの手すりにグルグル巻きに括りつけられた大きな笹。
この聖地にはあまり馴染みのないその植物に、ついオリヴィエは見入ってしまった。
「お茶が入りましたわ。」
背後からロザリアの声がして、オリヴィエは振り返った。
柔らかな白いワンピースは、通り抜ける風に揺れ、膝下で裾が踊っている。
凛とした大輪の薔薇のような補佐官服ももちろん美しいが、私服の彼女はたおやかな白薔薇のようだ。
それとも月に住む精霊か。
こんな夜は特にそう思ってしまう。
オリヴィエがバルコニーから部屋の中に入ると、トレーに透き通るグラスが二つ乗っていた。
精巧な切子細工。
大広間のシャンデリアを受けてあちこちに光をばらまくグラスには、薄茶の液体が入っていた。
彼女の好きな紅茶にしては、香りが少ない気がするのは、アイスにしているせいだろうか。
不思議に思いながらも液体を口に含むと、予想外の苦みと香ばしさに、オリヴィエは顔をしかめた。
「なに、これ。」
ふふっと口元だけで笑みをこぼしたロザリアが、同じように液体を口に含む。
やはり苦みを感じたのか、ほんの少し眉をひそめた。
「麦茶というのですって。夏になると、ある惑星でよく飲まれているらしいですわ。」
「もしかして、ルヴァ?」
特有の苦みはルヴァの執務室でよく飲まされる緑茶というものに、どことなく似ている気がする。
「ええ。この七夕だって、ルヴァが教えてくれたことでしょう? アンジェったら、本当に…。」
アンジェリークの思いつきはいつものことだけれど。
それを実現できるのは、ロザリアのおかげだろう。
今日もこの聖地にはない笹を持ってくるまで、ロザリアがあちこちに手配していたことをオリヴィエも知っていた。
けれどロザリアはそれを苦労とは思っていないようだ。
夜空に伸びる笹を見上げて、とても嬉しそうにほほ笑んだ。
「ご存じかしら?この笹に願い事を書いて吊るしておくと、その願いが叶うんですって。」
「へえ。」
織姫と彦星という、この行事のいわれは、散々アンジェリークとルヴァに聞かされた。
けれど、その願い事が叶うということについては、初耳だ。
「ようするに、一年に一度の逢瀬の喜びを私達にもおすそ分けしてくれるってことか。」
オリヴィエは笹を見つめ、小さく肩をすくめた。
「きっとアンジェもそれがお目当てなんじゃないかしら?」
いいながら、ロザリアはテーブルの上に置いてあったファイルから、折り紙の束を取り出した。
色とりどりの鮮やかな紙がテーブルの上に広がる。
「お好きな色をお取りになって。」
ロザリアは自分用にピンクの紙を一枚、選び出した。
その紙を半分に折り、またその半分に。縦に4分の一にしたところで、不意に部屋を出て行く。
オリヴィエもテーブルの上の紙を一枚手に取ると、ロザリアと同じように縦に4等分しておいた。
「願い事ね…。」
紙に書いて吊るしておくだけで叶うなら、この紙全部に書いてもかまわない。
オリヴィエが続けて何枚も紙を折っていると、鋏を手にしたロザリアが戻ってきた。
「まあ、そんなに願い事がありますの?」
驚いたように目を丸くするロザリアの前で、オリヴィエはまだ紙を折り続けている。
「これは、みんなの分。お子様たちなんて絶対に書きたがるでしょ? 後でわーわー騒がれるのは面倒だからね。」
「…ありがとう。」
外で笹も喜ぶようにざわざわと揺れていた。
紙に鋏を入れ、短冊を作っていく。
ロザリアが折った紙をオリヴィエが切るという動作を繰り返して、準備してあった紙のほとんどを短冊に変えた。
「残りはどうするの?」
オリヴィエが聞くと、ロザリアは4等分してあった紙をさらに小さくおり、そこに交互に切れ目を入れた。
「天の川を模しているそうですわ。」
ロザリアが広げた紙は、細かな切れ目が一面に入り、蛇腹のように伸びている。
「天の川って言うよりも、網、みたいだね。」
「そうですわね。…でも、綺麗ですわ。」
網目の隙間から覗くロザリアの青い瞳が綺麗で、まるで夜空のようだ。
オリヴィエも同じように天の川を切り込んだ。
他にもいくつか飾りを作り、笹にぶら下げると、急に笹が華やいで見える。
「なかなか風情があっていいじゃないか。ルヴァもたまにはイイ事いうね。」
「たまには、ですの?」
「ま、ね。 あ、陛下がらみでは時々あるか。」
さっきよりも温度を下げた風が笹の葉ずれを波の音に変える。
ゆったりと時間が流れるのは、この星空のせいだろうか。
思いがけずに二人きりになれた、この時間がもっと続けばいいと、オリヴィエは隣に立つロザリアをそっと盗み見た。
ふと目があって、頬笑みを交わす。
ロザリアは手にしていた短冊をもって、再び中へと入って行った。
「願い事、どうなさいます? みんなが揃ってからお書きになる?」
ロザリアがオリヴィエにペンを差し出した。
そのままペンを受取ってはみたものの、オリヴィエはペンを指の上でくるくると回すだけで何も書こうとはしない。
「あんたは書くの?」
同じようにペンを持って短冊に向かい合ったままのロザリアに声をかける。
ロザリアはびっくりしたようにオリヴィエを見た後、ほんのりと頬を染めた。
「どうしようかしら…。」
悩む顔もとても綺麗だ。
オリヴィエは困ったように短冊を手にしているロザリアを見ながら、残っていた麦茶を飲んだ。
このほんのりとした苦味は、今の想いによく似ている。
オリヴィエは自分の紺の短冊を手にとった。
もしもここに、『髪が赤くなりますように』だとか、『もう少し背が伸びますように』と書いたら、空の恋人たちはその願いを叶えてくれるのだろうか。
それとももっとストレートに『アイツになりたい』とでも書いたなら。
「オリヴィエ?」
ロザリアの青い瞳が訝しげにのぞきこんでいることに気がついて、オリヴィエはあいまいに微笑んだ。
見れば、ロザリアは願いを書いてしまったのだろう。
ペンを置いて、短冊を胸に抱いている。
「…なんて書いたの?」
悪ふざけのように、ロザリアの短冊を覗きこもうとすれば、彼女は身体を捩って、短冊を隠そうとする。
「教えてよ。あんたのお願い。」
あんまりやり過ぎて、本当にロザリアが去ってしまっても困るから。
オリヴィエはウインクを一つ向けて、じっと彼女を見つめた。
ロザリアは困ったように眉を寄せながら、頬を赤くしている。
伏し目がちの青紫の睫毛から、シャンデリアのライトの影が落ち、思わず見とれてしまった。
長いようで短い沈黙。
「わたくしのお願いは…。」
ぎゅっと短冊を押し付けていた手の力が弱まって、かさりと紙の音がする。
うつむいていたロザリアが顔をあげ、目があった。
「わ!すごい!ロザリア、飾りをつけてくれたのね!」
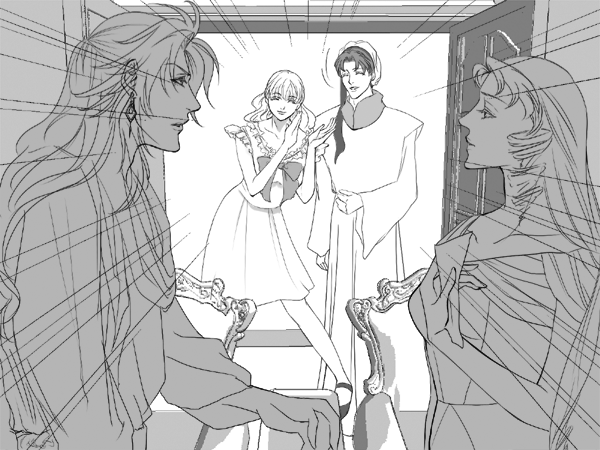
大声で手を叩きながらアンジェリークがドアを開けた。
その後ろに控え目に立つルヴァも、華やかになった笹を見て、うんうんと頷いている。
「短冊もある! ね、ルヴァ、一緒にお願い事を書きましょ!」
ルヴァの腕を引きずるように、テーブルに連れて行ったアンジェリークがたちまち願い事をいくつも書き始めた。
「ああ~、陛下、そんなにたくさんあるんですか~。」
「うん!!」
のんびりと書いたルヴァの短冊は『ずっと一緒にいられますように』の一言だけ。
「もう!やだ!当たり前でしょ!」
ばしーんとアンジェリークがルヴァの背中を叩く音がして、オリヴィエはぷっと吹き出してしまった。
ロザリアも楽しそうにほほ笑んでいる。
さっき、あと少しで見せてくれそうだった短冊は、またぎゅっと胸に押し当てられてしまっていた。
もう見せてくれることはないだろう。
残念な気がして、溜息が洩れた。
「お、ここかよ。なんかすげーな。」
「わあ!素敵だね。」
「大きいな~。」
次々に大広間に人が集まってくる。
ロザリアは持っていた短冊を自分のファイルに挟み込むと、お茶を出すために、グラスを並べ始めた。
色とりどりの切子のグラス。
ルヴァがその解説をはじめ、年少組がうんざりしたのを、アンジェリークがぽかりと叩く。
いつも通りの光景に、さっきまでの二人きりの時間が夢のようにさえ思えてくる。
ロザリアを手伝おうか、と、近付きかけて、オスカーが来たのに気がついた。
まっすぐロザリアの元に行くオスカーの姿を見て、オリヴィエは足をバルコニーに向ける。
星空に届きそうな笹。
けれど、てっぺんに結ばなければ、こんな小さな短冊の願い事は見えないのではないだろうか。
オリヴィエは真っ白な短冊を笹に結び、空を横切る天の川を眺めた。
「あの子の願いを叶えてあげてよ。」
風に揺れる笹の葉の答えは、オリヴィエにはわからなかった。
わいわいと騒がしい大広間。
思い思いに願い事を書いたり、お菓子をつまんだり。
七夕という口実は、みんなに楽しいひと時を与えているらしい。
麦茶をみんなにサーブしたロザリアは、再びファイルから短冊をとりだした。
「願い事は書いたのか?」
じっとバルコニーを見つめていたロザリアにオスカーが声をかけた。
バルコニーには大きな笹があるから、そちらに目を向けるのも不思議ではない。
けれどロザリアが見ていたモノが笹ではないことをオスカーは知っていた。
「ええ。でも、やっぱり叶いそうもありませんわ。」
アンジェリークが来た途端、離れてしまったオリヴィエ。
結局、オリヴィエは願い事も書いていなかったのだ。
自分にとっては甘い、二人きりの時間も彼にとっては退屈だったのだろう。
うつむいたロザリアの手の中の短冊が、オスカーの目にちらりと覗いた。
『この想いがあなたに届きますように』
彼女らしくないピンクの短冊が誰のためなのか。
オスカーはロザリアの手の中の短冊を横目にしながら、ペンをとった。
こんなほろ苦い気持ちになるのは、さっき口にした麦茶のせいかもしれない。
『この想いが叶いますように』
そう書いてペンを置いたオスカーは、書きあげたばかりの短冊をすぐに手の中で丸めた。
「どうかなさって?」
不思議そうに尋ねるロザリアに、「書き間違えた。」と短く答えた。
短冊に書いたくらいで叶う願いなら、とっくに自分の物にしている。
オスカーはグラスに残っていた麦茶を全部飲み干すと、バルコニーに目を向けた。
やはり彼女もそこを見ている。
まっすぐな熱い瞳。彼女の想いがどこにあるのかを、オスカーに嫌というほど教えてくれる。
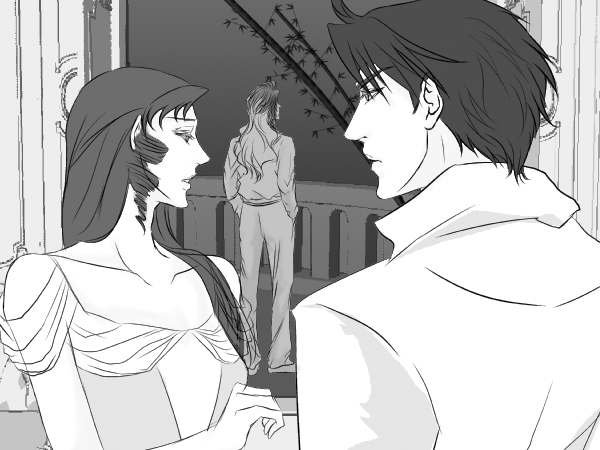
オスカーはもう一度ペンを持った。
『アイツになりたい』
そう書こうかと思って、真っ白なままの短冊を再び手の中で丸めた。
夜風に笹がさざめいている。
願いを叶えてくれる恋人たちの逢瀬が始まったころ、色とりどりの短冊が星空の下に揺れたのだった。
FIN
