記憶の隅に引っ掛かってはいるのに、どうしてもはっきりと思いだせない。
幼少のころから天才とうたわれ、研究者としてのエリートコースを歩んできた彼にとって、それは信じられない出来事で。
つい、口から出てしまったのだ。
「失礼ですが、以前、どこかでお会いしたことがなかったでしょうか?」
眼鏡のふちをくいっと持ち上げ、彼女の顔をまじまじと見つめた。
神秘の宇宙の色をした吸い込まれそうな青い瞳。
透けるような白い肌と、ほのかに赤みの差す頬の横で揺れる青紫の巻き毛。
見事なまでの美しさ。
確かにどこかで見たことがあると思ったのに。
その言葉を聞いたロザリアは、少し驚いたように瞳を丸くすると、すぐにゆっくりとほほ笑んだ。
「いいえ。お会いするのは今日が初めてですわ。これからはよろしくお願いしますわね。」
その優雅な微笑みに、やはりエルンストの頭の奥がちかちかと点滅を繰り返す。
見たことがあるのは確かなのだ。
ただ、それがいつ、どこでだったのかがまったく、思い出せない。
こんなことはエルンストの人生で、本当に初めてのことだった。
「本当に初めてでしょうか?」
繰り返したエルンストに、彼女の背後に控えていた人物から苦笑が漏れた。
「ずいぶんと懐かしい声のかけ方じゃない? どこかで会った…なんて、ナンパのセリフとしては少しイージーな気がするけど。」
華やかな衣装と整った容姿。女性とみまごうばかりのあでやかな姿。
オリヴィエはにやりと笑みを浮かべ、エルンストを見ている。
一瞬遅れて、彼の言葉を理解したエルンストは、「いえ、そういう意味ではありません。」と、再び眼鏡を持ち上げた。
「御冗談が過ぎますわよ。」
ロザリアがオリヴィエを軽く睨みつけると、途端にエルンストの心臓がギュッと縮まった。
呼吸困難と血圧上昇。
分析は冷静にできるのに、対処の方法はわからない。
「どうかなさいまして?」
さらに加わる頭痛。
その日から、エルンストは制御できない体調不良を時々感じるようになったのだった。
「では、そのようにお願いいたしますわ。」
新宇宙のデータを手渡すと、ロザリアは付箋のついた個所へとページをめくった。
分厚いデータを彼女はすべて読みこんでいる。
女王候補たちに的確なアドバイスを送るためにも、勉強は欠かせないと思っているようだった。
「エルンストはどうお考えになりまして?」
自分の意見を言うよりも前に、ロザリアは必ず相手の意見を聞く。
そのおかげか、初めはあまり自分の意見を言えなかったコレットも、この頃はエルンストにきちんと発言できるようになっていた。
研究院にとってもそれは喜ばしいことで、育成の成果が目に見えて表れている。
「そうですね。私はこの数値からして、次の段階に進むべきではないかと考えています。」
ロザリアの持つデータ表の数値を指差すと、激しい頭痛に襲われた。
思わずこめかみを押さえたエルンストをすぐ隣に立つロザリアがじっと見つめている。
エルンストは眉を寄せると、くいっと眼鏡を上げた。
「申し訳ありません。少し席をはずしますので、詳しいデータはあちらの者に聞いてください。」
不整脈と体温の上昇。
このごろ起こる症状としては最も多いものだ。
エルンストは給湯室でコーヒーメーカーをセットしながら、考えていた。
聖地に来る前は、こんなことはなかったのに、まったく理解不能だ。
コツコツと綺麗なリズムで聞こえるヒールの音とともに、ふわりと鼻先をある香りがかすめる。
また、かっと熱があがり、エルンストは顔をしかめた。
「もう気分はよろしくて?もし、体調がすぐれないようなら、少しお休みされてはいかがかしら?
このところずっと研究院に詰めていらっしゃるそうですわね。」
「いえ。御心配には及びません。」
エルンストがコーヒーメーカーから目をそらさずにきっぱりと言い切ると、すぐにコーヒーがポットに零れおちてきた。
給湯室はそれほど広くない。
おそらく4人ほどが中に入ればいっぱいになってしまうだろう。
コーヒーの香りのほうが強いはずなのに、なぜ。
こんなにも薔薇の香りばかり、気になってしまうのか。
「そう…。でも、本当に…。」
「いえ。大丈夫です。申し訳ありませんが、休んでいる暇などありません。」
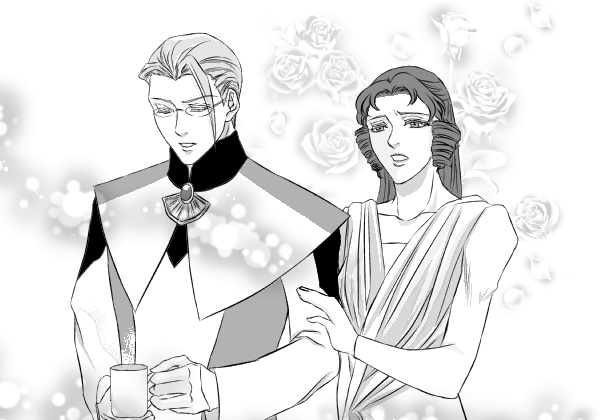
コーヒーをカップに移し、くるりと向きを変えると、心配そうなロザリアの顔が目に入る。
息がつまりそうになるのは、給湯室が狭いからだ。
それ以外に特に理由も思いつかない。
「失礼します。」
わきへよけたロザリアのすぐ横を通り抜けると、自分の席へと向かう。
なんだかひどく喉が渇いて、エルンストはすぐにコーヒーを飲み干してしまったのだった。
研究院でデータを受け取ったロザリアは、その足でオリヴィエの執務室に向かった。
ちょうど午後のお茶の時間。
出迎えたオリヴィエは手際よくロザリアの好きな紅茶を淹れると、向かいに座った。
話をしながらお茶を飲んでいた時、ふと、ロザリアの口からため息がこぼれる。
「どうしたの?なんか悩み事?」
二人でお茶を飲むことは決して少なくはない。
むしろ、女王以外でロザリアとこうして過ごす守護聖は自分しかいない、とオリヴィエは思っていた。
そして彼女から訪れてくるときは、たいてい何かを話したいとき。
迷い猫がいた、とか、おいしいケーキのレシピをみつけた、とか、些細な話題だが、嬉しそうな彼女を見るのは楽しい。
もちろん、自分にしか話さないだろう悩み事を聞くのも、自尊心がくすぐられる貴重な時間だ。
「ええ…。」
青紫の睫毛を少し伏せ、憂いを帯びた青い瞳がカップを見つめている。
少しして、ロザリアは思い切ったように口を開いた。
「わたくし、エルンストに嫌われているみたいなんですの。」
「え?」
彼女は長いため息をつくと、カップを置いた。
「研究院でなにかを尋ねても、ほとんど答えてくれませんし、データの受け渡しも助手の方任せですの。
初めのころはきちんと対応してくださいましたのよ?今ほど無表情でもありませんでしたわ。
なんだかわざと避けられているような気がして…。今日も、わたくしがお話しようとしたら、わざわざお茶を飲みに行かれて。」
まだありますわ、とロザリアはいかに自分がエルンストに避けられているのか、ということを延々と語り始めた。
聞けばたしかにオリヴィエの知るエルンストとは少し態度が違うようだ。
そのこと自体は、別にいいのだけれど。
オリヴィエはなんとなく落ち着かない気持ちでお菓子をつまんだのだった。
数日後、ちょっとした用事を思い出したオリヴィエは、研究院へと足を向けた。
外は見事な青空だというのに、研究院という場所は、なぜこんなに白いのだろう。
オリヴィエはまっすぐに延びるリノリウムの床を眺めながら、小さくため息をついた。
こんなつまらない場所にいたら、半日で窒息してしまいそうだ。
きょろきょろとあたりを見回したオリヴィエは、目当ての人物を発見して、言葉を飲み込んだ。
ちょうどロザリアがいる。
オリヴィエは壁の隅に隠れると、二人の様子を観察することにした。
エルンストは分厚いデータの束をロザリアに手渡した。
ほんの3日くらいの間で、データは3cmくらいの厚さにまでたまってしまう。
毎日渡さなければならないはずのデータが溜まってしまったのは、ロザリアが研究院に来なかったせいだ。
久しぶりに見る彼女の横顔は、やはりどこかで見たことがある気がする。
なんとなく、もやもやと気分が悪くなった。
「ずいぶんたくさんありますのね。」
パラパラとページをめくりながら、ロザリアが微笑みかける。
エルンストは、なぜかかっと頭に血が上るのを感じた。
「失礼ながら、ロザリア様がサボっていたせいではありませんか?日々データは蓄積されていきます。
もし、ご興味が失せたのでしたら、もうおやめください。このような手間は我々にとっても時間の無駄です。」
「サボっていたですって?」
ロザリアが研究院に来れなかった理由をエルンストも知っている。
コレットが熱を出して倒れ、その看病に当たっていたのだ。
エルンストがデータの説明でコレットのもとを訪れた時に、コレット自身から聞いたのだから間違いはない。
けれど。
「それだけのデータを読み込むには、お時間がかかることでしょう。質問は後日にしてください。」
くるり、と背を向け、エルンストは自分の席に戻った。
眉を寄せたロザリアの顔が目に入ると、動機が激しくなる。
不整脈の症状は今に始まったことではないが、今日は一段と激しいようだ。
なぜ、彼女に対しては、あんな言い方をしてしまうのだろう。
いつもならセーブできる感情が、ついこぼれてしまうのだ。
「ロザリア。」
突然現れたオリヴィエが彼女に声をかけているのを見ると、一気に頭痛が激しくなった。
動悸、息切れ、そして、めまい。
少ししてロザリアの声が聞こえなくなったかと思うと、視界が暗くなり、目の前に影が落ちる。
「ちょっといい?」
こめかみを押さえていたエルンストは、オリヴィエに追い立てられるように、外へと連れ出されたのだった。
白ばかりの研究院から外へ出ると、空は目に痛いほど青かった。
黙ってついてくるエルンストは、いつも通り感情のない様子で、よくできたアンドロイドみたいだ。
そう。この彼ならば、よく知っている。
冷静で、毅然としたいつものエルンスト。
さっきのように、皮肉めいた口調で不愉快な感情をあらわにする彼を、オリヴィエは初めて見た。
「あのさ。ロザリアとケンカでもしてるの?あの子、あんたになんかした?」
研究院の裏の木陰は、滅多に人が通りかかることはない。
今日も静かに木々の葉が擦れるだけ。
その静けさのおかげで、エルンストの呼吸が少し変化したのにオリヴィエは気づいた。
「いえ。なにもありません。…なぜそのようなことを?」
「お節介かとは思ったんだけどさ。ロザリアも気にしてるみたいだし、さっきみたいなのを見せられちゃうとね。気になるじゃない?」
オリヴィエは腕を組むと、エルンストを眺めた。
「なにか理由があるなら言ってくれない?私から、あの子にも言っておくからさ。」
ぴくり、とエルンストのこめかみが動く。
「なにもありません。ただ、体調がすぐれないだけです。」
「へえ。…どんなふうにすぐれないわけ?」
好奇心なのか、警戒心なのか。多分そのどちらもだろう。
オリヴィエはエルンストの言葉を待った。
「そうですね。たとえば、急に不整脈が起きたり、熱が上がったり。訳もなくイライラしたり、頭痛が起きることもあります。」
そこで、エルンストはふと思いついたように、オリヴィエを見た。
「一人の時に、なぜか胸が苦しくなることも。…聖地の気候が私には合わないのかもしれません。」
「へえ…。」
その症状を、オリヴィエは良く知っていた。
ドキドキしたり、時には胸を締め付けられたり。
今、まさにオリヴィエ自身もそれに悩まされているのだから。
「そういえばさ、ロザリアを見たことがあるって話。なんだったか思いだした?」
エルンストはそわそわと眼鏡を上げると、首を振った。
「いえ。お恥ずかしい限りですが、思い出せないのです。どこかでお会いしたことがあるのは間違いないのですが。」
「そっか。」
「…ロザリア様もなにかおっしゃっておられましたか?」
「ん~~。あんたのことは言ってたような言ってないような。」
はぐらかすようなオリヴィエに、明らかにイライラとしているのがわかる。
「まあ、よくお茶するからさ。私たち。」
むっとエルンストの眉が不愉快そうにひそめられた。
まったく、彼女の話題になった途端に、眼鏡を上げる回数が増えたことさえ本人は気が付いていないのだろう。
もっと突っ込みたいような気もしたが、あまり突っつきすぎて、エルンストが気がついてしまうのも困る。
「とにかくさ、なんでもないなら、そう言ってあげてよ。なんでもないってさ。」
「はい。お気づかいいただいて、申し訳ありませんでした。」
折り目正しい礼をして、エルンストが去っていくと、オリヴィエは足元の小枝を拾いあげた。
「悪いけど、あんたに教えてあげるわけにはいかないんだよね。」
掌でぽっきりと二つに折れた小枝を投げ捨てると、オリヴィエはちいさく、溜息をついた。
その日、エルンストは朝から不調だった。
なんとなく頭が痛いような、めまいがするような、不思議な感覚がする。
ふと、パソコンのディスプレイに疲れて、目を抑えた。
あれから、ロザリアは一度も研究院を訪れてこない。
データだけは補佐官付きの女官が取りに来るものの、彼女自身の姿を見ることはない。
目を閉じたエルンストの脳裏に、あの日のロザリアの顔が浮かぶ。
動悸や熱が一気に上昇し、頭痛が一層激しくなった。
「どうかなさいまして?」
背中から掛けられた声に、思わず立ち上がったエルンストは、目の前にいるロザリアをまじまじと見つめた。
久しぶりに見る彼女の瞳は、やはり吸い込まれそうなほど美しい青。
「ずいぶんお久しぶりですね。もう、育成のデータは無用なのだと思いました。」
また、嫌味な言い方をしてしまった、と思わず眼鏡を持ち上げた。
この理解しがたい感情は何なのだろう。
彼女の姿を見た瞬間、最初に感じたのは嬉しさ。そして、次に恨めしさ。
甘いものと苦いものがない交ぜになり、言葉を飾ることさえできなくなってしまうのだ。
「ごめんなさい。もう一度最初からデータを読み込むことにしましたの。一週間ほどかかりましたけれど、新しい疑問点も出てきましたわ。」
分厚いデータ集は付箋の数がぐっと増え、赤い下線が数多く引かれているのが見える。
「そう言えば、オリヴィエに聞いたんですけれど、体調が良くないそうですわね。なにかあったら、遠慮なさらずにわたくしにおっしゃって。」
『オリヴィエ』と、ロザリアが言った瞬間、胸がギュッと掴まれたように痛くなった。
不整脈を通り越して、心筋梗塞にでもなったのか、と思わず胸のあたりを掴む。
でも、この痛みは、心臓というよりも、もっと奥深いところからきているような気がする。
突然、世界がぐるぐると回り出すと、エルンストの目の前が暗くなった。
「エルンスト?!」
ロザリアの声が遠くに聞こえる。
そこで意識が途切れた。
朦朧とした意識の中に、鮮やかな花の香り。
エルンストがうっすらと目を開けてみると、そこにロザリアがいた。
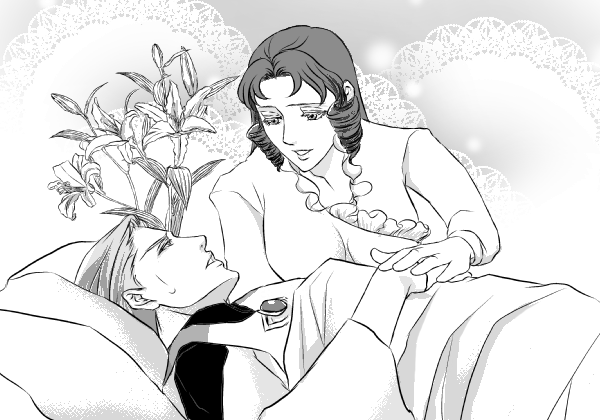
「気が付きましたのね。」
ロザリアは抱えていた白い花をベッドの隅におくと、エルンストに近づいてきた。
白い天井が目に入り、エルンストは自分がベッドに寝かされていることに初めて気がついた。
あわてて起き上がろうと、腕に力を入れてみても、まるで鉛にでもなったように全く力が入らない。
かろうじて、目だけを動かすと、ロザリアはベッドサイドに椅子を近付け、すぐそばに座った。
「過労だそうですわ。研究院の方にお伺いしましたら、このところずっと、泊り込んでいらしたらしいですわね。
そんな無理はなさらないでくださいませ。…いい機会ですわ。少しお休みになって。」
ずれた布団をかけ直し、ロザリアは優しく微笑んだ。
その笑顔に、エルンストの頭の中がまた点滅を繰り返している。
思いだそうと頭をひねるエルンストの沈黙を肯定と受け取ったのか、ロザリアは立ち上がると、ベッドサイドにおいた花束を抱えあげた。
強い芳香は、純潔の花。
華やかな百合の香りが部屋全体を包みこんでいる。
再び意識が薄らぐなかで、百合の花を持つロザリアが瞳に焼きついた。
美しい横顔は、ずっと心の奥に残してあった思い出に似ている。
やっと思い出すことができた安心感からか、エルンストは再び深い眠りへと落ちていったのだった。
機械のように正確なノックの音にせかされてドアを開けてみると、エルンストが立っている。
オリヴィエは珍しい客に少し目を丸くして、彼を中へと招き入れた。
エルンストが倒れて3日。
今日から研究院に復帰することはもちろん知っている。
だが、朝一番でオリヴィエの部屋にやって来るような理由が思いつかなかった。
「朝から申し訳ありません。オリヴィエ様にどうしてもお伝えしたいことがあるのです。」
「そ、そうなんだ。いったい、なに?」
たじろぐオリヴィエに、いたってまじめな様子で、エルンストはポケットを探ると、一枚のカードをとりだした。
「これです。」
「は?」
思わず聞き返したオリヴィエに、エルンストはカードをさらに突き出すようにして近付けた。
「ロザリア様にそっくりだと思われませんか?」
オリヴィエはエルンストが突き出したカードを見た。
青い長い髪を背に垂らし、一本の百合を差し出す天使の絵。
優しく微笑む姿も、美しい横顔も。
確かにロザリアによく似ている。
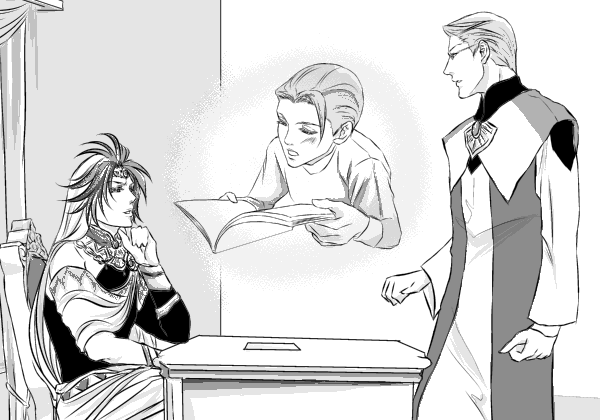
「ホントだね…。確かに似てるわ…。これ、どうしたの?」
エルンストはななぜか言葉に詰まったように咳払いをした。
「子供の頃、母が読んでくれた本に出てきた絵なのです。」
「へ~~~。」
綺麗な絵であることは間違いない。
けれど、カードにしては紙質も良くないし、少し不自然な構図で、なにかの絵の一部のようにも見える。
オリヴィエの疑問に気づいたのか、エルンストは小さくため息をついた。
「…実はこれは初めからカードだったのではありません。」
「どういうこと?」
突っ込んだオリヴィエに、エルンストは眼鏡をくいっと持ち上げた。
「どうしても欲しくて、勝手に本から切り取ってカードに加工したのです。携帯にも便利ですし。」
ようするに、それほど心奪われた、ということなのだろう。
彼にとっての初恋の女性。
それが純潔の天使だというところが、いかにも彼らしい。
幼い日のエルンストが本を切り取る様子を思い浮かべて、オリヴィエは笑みがこぼれそうになった。
「もうすっかり忘れていたのですが…。どこか心に残っていたのかもしれません。」
エルンストはカードをポケットに戻すと、オリヴィエに一礼した。
「これで、私の勘違いではないと御理解いただけたと思います。私も思いだすことができて、すっきりしました。」
どこか晴れ晴れとした表情のエルンスト。
けれど、本当の問題はすでにそれではない。
コンコンと、聞きなれたノックがして、ドアが開いた。
途端に漂う薔薇の香りで、訪問者がロザリアであると、すぐにわかる。
「まあ、エルンスト。すっかり良くなったようですわね。安心しましたわ。研究院の皆様がお待ちでしたわよ?」
まさに天使の微笑み。
青紫の髪こそベールに隠されているものの、その美しさは、カードの天使よりも見る者の目を奪う。
彼女自身は、少しもそのことに気が付いていないようだけれど。
心まで奪われたものが、ここに二人。
「オリヴィエ、陛下が呼んでいますの。多分また、ダイエットの話だと思いますけれど、あとで、女王の間にいらしていただけるかしら?」
「ん。わかったよ。後でね。」
そよ風のように彼女が去った後、直立不動のエルンストをチラリと見た。
もういい加減、自分の気持ちにも気がついただろう。
ところがエルンストは右手で胸を抑えたまま、オリヴィエにくるりと顔を向けた。
「やはり気候が合わないのでしょうか。疲労は取れたはずなのに、前よりも不整脈がひどくなったようです。
しかも、ロザリア様を見ると、思いだせなかった時よりも、もやもやした気持ちが残るのですが…。まだ、忘れていることがあるのかもしれません。」
考え込むように首をかしげ、ブツブツ言いながらエルンストが部屋を出ていく。
一人残ったオリヴィエはスプリングがきしむほどの勢いで、ソファへと座り込んだ。
「絶対教えてなんかやらないからね!」
そう、その気持ちが恋だなんて。
その日から、再び、エルンストは謎の体調不良に悩まされるようになった。
「百合にもアレルゲンがあるようですね。」
ロザリアが研究院に届けてくれた百合の花を見るたびに、ぎゅっと胸が痛くなる。
激しい動機と血圧上昇も、相変わらず。
しかも、天使のカードを見るたびに、ロザリアの幻覚が見えるのだ。
カードの絵が似ているせいかとも思ったが、どうもそれだけではないらしい。
「一体、何なんでしょうか・・・?」
その原因をエルンストが知るのは、まだまだ先の話なのだった。
FIN
