このところの天気はまるで猫の目のように変わりやすい。
下界だけではなく、この飛空都市でさえも。
女王の力と天気が関係していることを、オリヴィエは守護聖になってから初めて知った。
今日の不安定な天候も、今の宇宙そのものだ。
さっきまで、眩しいほどの太陽が輝いていたというのに、ちょっと庭園まで散歩の足を伸ばしたところで、降り出した雨。
叩きつけるように激しい雨が、オリヴィエの頭上に降り注いで来る。
メイクに雨は厳禁だ。
慌てて、東屋の中に走り込むと、そこに先客がいた。
東屋の屋根を叩く雨音は、スネアドラムのように激しい。
オリヴィエが思わず耳をふさぎたくなるほど、バラバラのリズムで叩く音は耳障りだ。
その激しい音の中。
ロザリアはじっと睫毛を伏せている。
規則正しく動く胸元で、オリヴィエは彼女が眠っているのだと思った。
疲れているのだろう。
女王候補として、ロザリアは常に完璧を目指している。
もとより完璧な人間など、この世にいるはずがないのだから、完璧であろうとするためには、それ相応の努力が必要だ。
アンジェリークが守護聖たちとお茶を飲んでいる時でも、ロザリアは一人、図書館で勉強していた。
孤高の薔薇は美しい。
けれど、強い風で折れてしまうのではないかと気になった。
つい支えたい、と手をかけたのは、オリヴィエにとって必然で。
「思い」が「想い」に変わるまで、そう時間はかからなかった。
育成のお願いよりもお話の時間ほうが増えた時、初めてロザリアが弱音をこぼした。
「一人で悩むよりは、誰でもいいから頼ってごらん。」
「…頼ってもよろしいのでしょうか?」
まっすぐにオリヴィエを見つめた青い瞳。
魅入られるように言葉にしていた。
「誰でもいいなんて、嘘。…私にしてよ。」
美しい薔薇を自分の手で守りたい。
それが二人の始まりだった。
ますます強くなる雨の音。
オリヴィエはロザリアが目を覚まさないように、そっと両手で彼女の耳を覆った。
手の甲には青紫の柔らかな巻き毛。掌には、陶器のように滑らかな白い頬が触れる。
音のない世界で、ロザリアはどんな夢を見ているのか。
夢の守護聖なのに、彼女の夢に触れることができないのがもどかしい。
目を伏せたまま、ロザリアが淡く微笑んだ。
ほんの少し動いた桜色の唇が、鮮やかに瞳に焼き付いて。
オリヴィエはその唇に、そっと自分の唇を近付けた。
触れるだけで、すぐに離れていくような、そんな優しい口づけ。
そして、おとぎ話のように、ロザリアが目を開けた。
「起きてたの?」
「はい。雨の音を聞いておりましたわ。でも、急に聞こえなくなって。」
「ごめん。…怖かった?」
「オリヴィエ様だとわかりましたから。」
「そう。」
ロザリアが再び目を閉じる。
今度はゆっくりと、オリヴィエは唇を重ねた。
柔らかくなる雨の音。それと入れ替わるように、激しくなる鼓動。
真夏の雨は降り始めと同じように、突然消えていった。
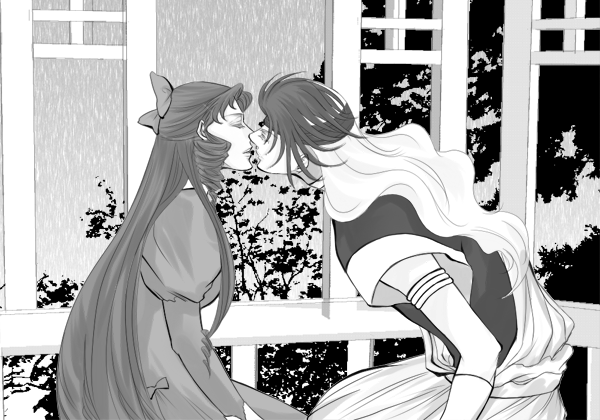
一度触れ合った唇は、もうその熱を知らない頃には戻れない。
唇から、全身へ。
すぐに体中でお互いの熱を共有した。
「もう、女王にはなれないよ。」
オリヴィエはロザリアの背中に指を滑らせ、長い髪を梳いた。
そしてぴったりと溶け合うほどに素肌を触れ合わせる。
「女王にはなりませんの。」
ロザリアが恥ずかしそうに、でも嬉しそうに笑った。
試験が終わり、ただのロザリアに戻ったら、夢の守護聖の恋人として聖地に迎え入れればいい。
前例がないかもしれない。反対する者もいるかもしれない。
だから、二人の関係は誰にも知らせなかった。
真夜中。
オリヴィエは暗い闇の中を、月明かりを頼りに歩いていた。
昼間ならなんども通った道でも、油断はできない。警備兵や使用人が真夜中でもたくさんいる。
その中の誰かにでも見つかったら。
ざわざわと草をかき分ける音が響いて、オリヴィエは壁際に息をひそめた。
行き過ぎる人の気配に、ホッと胸をなでおろすと、そびえたつ城壁を見上げる。
あの、光の消えた窓の向こうに彼女がいる。
女王は純潔でなければならない、と、聞いていた。
だからロザリアが女王になることはないと信じ込んでいたのだ。
けれど、宇宙が選んだ女王はロザリア。
選択の余地もなく、彼女は連れ去られてしまった。この、豪奢な牢獄の中へ。
アンジェリークが補佐官になり、即位は滞りなく進んだ。
古い宇宙から新しい宇宙へ移動し、なにもかもが新しい世界に変わる。
女王としてもロザリアは完璧だった。
サクリアの采配も、宇宙の統治も、ジュリアスでさえ無条件に褒め称えるほど、歴代の女王の中でも突出した手腕を見せている。
女王候補の時と、同じ。だれもが彼女こそが女王にふさわしいと認めている。
けれど、その完璧な女王の顔の向こうに、オリヴィエは影を感じてしまった。
輝いていた青い瞳から、徐々に光が失われている。
美しすぎる孤高の薔薇が、誰に頼ることもできず、ゆっくりと萎れていくのが目に浮かんだ。
手を伸ばせるなら、なんでもしてあげたいのに。
女王になったロザリアには、言葉をかけることもできない。
いつしか、真夜中過ぎに宮殿に来るのが日課になっていた。
中庭から見上げる彼女の部屋は、いつも明かりがついていない。
眠っているのだろうか。
夢の守護聖なのに、彼女の夢に触れることはできない。
以前にも同じことを考えた。
けれど、あの頃は、同じ未来なら見ることができた。
明かりがついていないのに、ロザリアが眠っていないと知ったのは、ある月の眩しい夜。
彼女の部屋のバルコニーから、花が降って来た。
月明かりを影に変えながら、舞い落ちてくる花びら。
白いバラの花びらが何枚も何枚も、まるで華吹雪のように降り注いできた。
「眠れないときはね、数を数えるとイイよ。どっかの星では、羊とかを数えるんだって。」
「羊? もっと他に数えるものはなかったのかしら?」
「そうだね。…たとえば、花びらとか?」
「そのほうがずっと綺麗ですわね。 もし、わたくしが眠れないときは、薔薇の花びらを数えることにしますわ。」
「あんた、いつもよく寝てるけど。 寝かせたくない時も、寝ちゃうじゃない。」
「…いじわる。」
彼女と交わした寝物語。
ロザリアは眠れないのかもしれない。
ベール越しに見える疲れた顔は、夢の世界を拒んでいるせいなのだろうか。
見上げても、バルコニーの影に隠れて、彼女の姿は見えない。
けれど、日ごとに増えていく、舞い落ちる花びらの数。
その花びらがロザリアの涙のように思えて、放っておけなくなった。
「陛下。」
肩を叩かれて、ようやくロザリアは自分が呼ばれているのだと気がついた。
女王になってから数カ月が経つというのに、まだ実感がない。
実感がないというよりも、まるで全てが夢のような気がする。
今、ここで目がさめれば、傍にオリヴィエがいて。
『なんの夢を見てたの? ちょっと苦しそうだったよ。』と、目じりにキスを落としてくれるような。
「陛下?」
さらにかけられた声でロザリアははっと顔を上げた。
心配そうにのぞきこむ、アンジェリークの緑の瞳。
「ごめんなさい。なんだったかしら?」
「あのね、これ。」
アンジェリークが差し出したのは、ピンクのチュールのリボンが結ばれた小さな箱。
「…オリヴィエから。陛下に渡してほしいって。」
「オリヴィエから?」
箱を受け取るロザリアの手が震えた。
女王になってから一度も触れたことのない、言葉を交わしたこともない、愛しい人。
もう、彼は自分のことなど忘れてしまったと思っていた。
身体の中に、あの頃の熱が蘇ってくる。
いまでも息ができないほど、彼を愛しているから。
アンジェリークが去った後、ロザリアはそっと箱を開けた。
小さな箱の中から、溢れだしたのは、白い花びら。
昨夜、この部屋から落ちた白いバラの花びらが、箱の中におさめられていた。
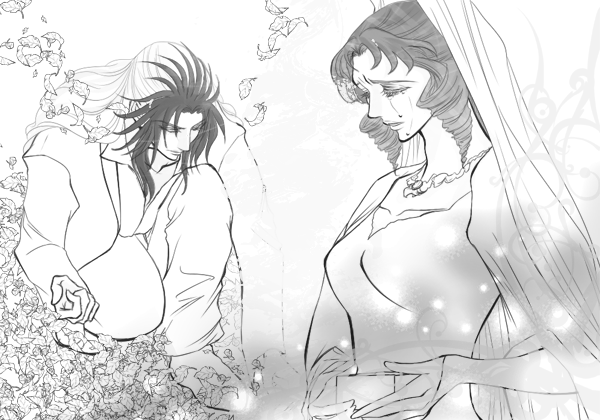
「オリヴィエ…。」
数え切れないほどの花びらを、一枚づつ拾う、彼の姿が目に浮かんだ。
自分が落した花びらを、受けとめてくれる人がいる。
ただ、それだけで、一人きりではないのだと、愛は続いているのだと、知ることができた。
女王になってから抑えていた想いが、堰を切ってあふれ出してくる。
久しぶりに声を出して泣いたロザリアは零れおちた花びらを、再び箱の中に収めた。
たとえ誰にも伝えることができなくてもいい。
ずっと心の中で想い続けていれば、いつか、叶う日が必ず来る。
その時までこの花びらたちは、オリヴィエと自分を繋ぐ証になるだろう。
執務室でぼんやりと空を眺めていたオリヴィエは、突然降りだした雨に窓を開けた。
ロザリアは今頃、あの花びらを見てくれているだろうか。
窓から手を伸ばし、雨の温度を確かめてみた。
どこかぬくもりのある暖かな雨。
この雨が彼女の涙だとしたら、少なくとも悲しいだけの涙ではないはずだ。
花びらを集めることで、彼女が眠るまで傍にいる、と伝えたかった。
抱きしめることはできなくても、最後の花びらが落ちるまで、必ず傍にいる、と。
叩きつけるように降り注ぐ雨なのに、空の向こうは明るい光が見えている。
まるで真夏の雨のように。
雨が通り過ぎたすぐ後には、晴れ渡る空が輝くように。
いつかきっと、また二人で過ごせる時が来るはずだ。
その時が来るまでは花びらを集めて贈り続けよう。
彼女が女王でなくなる、その日まで。
FIN
