11.
「あんな所から出るだなんて思ってもみませんでしたわ。」
裏口から店を出ると、二人は白い月明かりの中、まるで逃避行のように、路地を歩いていた。
けれど、高揚した気分に反して、体は少し疲れている。
オリヴィエは目当ての広場にたどり着くと、噴水の縁に腰を下ろし、隣に座るようにロザリアを手招きした。
街灯に照らされた噴水は、宝石箱のように煌めいて、銀の飛沫を散らしている。
賑やかな通りの喧騒もここまでは届かないのか、聞こえるのはかすかに水の流れる音だけ。
座った途端に大きなため息がこぼれて、ロザリアは自分が思っていたよりも緊張していたことに初めて気が付いた。
今更ながら、人前で歌ったことが恥ずかしくてたまらない。
「疲れた?」
わずかな距離の先にあるオリヴィエの瞳。
ロザリアはドキドキを隠すように、小さく頷いて俯いた。
「少し…。 でも、大丈夫ですわ。」
疲れた、なんて言えば、この楽しい時間が終わってしまいそうで。
今はただ、少しでも長くこうしていたかった。
「さっきの歌、すごく良かったよ。」
ロザリアは俯いたまま耳まで赤くなった。
大勢の人の前よりも何よりも、オリヴィエの前だったことが本当は一番恥ずかしい。
「いいえ。 オリヴィエ先生のピアノの方が、素晴らしかったですわ。」
「私のはタダの見様見真似だから。
あんたの歌の方が…ずっと…素敵だった。 本当にね。」
真剣な声は彼の本心のような気がして、ロザリアはますます赤くなってしまった。
「わたくしが知っているのは、本当にあの曲だけなんですの。」
「どこで知ったの?」
興味ありげに尋ねられれば、隠すことでもない。
「中等部のころまで、礼拝堂で讃美歌を歌う活動をしていたんですの。
週末のボランティアでしたけれど、とても楽しくて。
そこにピアノを弾きに来ていた方が、いつも活動の最後に聴かせてくださったのが、あの曲なんです。
毎週でしたから、いつの間にか覚えてしまって。」
小さな思い出。
父にもっと勉強時間を増やすように命じられて行けなくなってしまったけれど、礼拝堂で歌うのは大好きだった。
たぶん、今日、歌えたのも、あの経験があったからだろう。
「ふうん。 …もしかして、その人があんたの初恋の人?」
「え!」
眉を寄せ、つまらなそうに言うオリヴィエにロザリアは絶句した。
「その方、女性ですわ。
音楽大学の生徒で、今は楽団に入って活動されていますの。」
「…そうなんだ。」
「ええ。 とても綺麗な方で、あ、学園の卒業生でもいらっしゃるんですのよ。」
無邪気に話すロザリアに、オリヴィエは苦笑した。
あんな顔をして、思い出話をされて。
嫉妬した、なんて、彼女は夢にも思っていないに違いない。
丸い月が噴水の水面に滲んでいる。
すっかり高く昇っているところを見ると、もうかなり遅いのだろう。
オリヴィエは携帯で時刻を確かめた。
そこに記された数字は、もうシンデレラにも遅すぎる。
「そろそろ帰ろうか。 」
オリヴィエが立ち上がると、ハッとロザリアが口を結んだ。
何を言えばいいのか、困惑したように、ぎゅっとスカートを握りしめている。
「アンジェリークの家まで送るよ。
彼女の家は知ってるの?」
ロザリアが頷く。
夢の時間は本当にあっという間だ。
腕によりをかけたメイクはまだしっかりと残っているし、付けた香水の香りも変わってはいない。
でも、確実にオリヴィエの中の彼女への想いは変化している。
ずっと感じていた、教師と生徒という壁。
一度、その壁のない状態で、彼女を知りたかった。
願いは叶ったけれど、本当は叶わない方がよかったのかもしれない。
再び壁を意識するには、忘れたくないことが多すぎる。
それに壁は無くなったわけではないのだ。
もしも彼女が飛び越えようとしてきても、オリヴィエは手を差し伸べることはできない。
今はまだ教師だから。
ロザリアもまた、オリヴィエのシルバーの靴のつま先に光る月明かりを眺めていた。
帰らなければいけない事はわかっている。
アンジェリークだってきっと待っているはずだから。
けれど、もう少し。
教師ではないオリヴィエと同じ時間を過ごしたかった。
女性のようにメイクをしているオリヴィエを、生徒のロザリアはきっと見ることはできなかっただろう。
だから、メイクをした彼の顔を見た時、驚きよりも嬉しさが大きかった。
ロザリアにその姿を見せてくれたことが。
ただの生徒ではなく、一人の女性として、ロザリアに向き合ってくれたことが。
それはロザリアが、ずっと願っていたこと。
「オリヴィエ先生。
聴いてほしいことがあるんですの。」
先に歩き出していたオリヴィエの元へロザリアは駈け出した。
今、言わなければ。
きっと二度と言えない。
「なあに?」
振り返ったオリヴィエの瞳が、決意を秘めたロザリアの姿をとらえる。
キレイで…愛おしい。
けれど、彼女から想いを告げられたら、突き放さなければいけないと覚悟していた。
「わたくし、高等部を卒業したら、そのまま学園の大学に進みますわ。」
それは、この学園のほとんどの生徒が選ぶ道。
特にロザリアのように幼稚舎からずっとこの学園で過ごしてきたような生粋のお嬢様であれば当然だろう。
でも、彼女がここで言いだした事には、きっと何か意味がある。
オリヴィエは黙って、彼女の言葉の続きを待った。
「経営学部で、会社経営を学んで、必修の単位を揃えたら、経営学修士の資格を取るために、留学する予定ですの。
短くても2年。 もしかすると、それ以上になるかもしれませんわ。
父は婿を取ればいいと言いますけれど、わたくしは自分で家を継ぎたいと思っていますの。
誰かに任せて、頼っていくなんて、嫌ですもの。」
カタルヘナ家はいくつもの会社を経営する財閥で、一人娘の彼女は唯一の跡継ぎだ。
好むと好まざるにかかわらず、それはロザリアに常について回る運命。
ロザリアらしい、とオリヴィエは思った。
生真面目で、優秀なロザリアなら、きっと会社を引き継いでいけるはずだ。
経営者として立つ頃、彼女は今よりももっと輝いて美しくなっているに違いない。
「でも、これはまだ夢なんですの。 そうなれたらいい、というだけで。
わたくしは、まだ、子供で、何もできていなくて。
でも、夢に近づけるように努力して、いつかきっと、先生にふさわしいような、素敵な女性になれるように頑張ると約束しますから…。
本当に本当に頑張りますから。
ですから…。
先生。 その時まで…。」
その先の言葉が出てこなかった。
それはロザリアの希望で、オリヴィエを縛ることなどできない。
黙り込んだロザリアの両肩に、オリヴィエの手が触れた。
抱きしめようと思えば、すぐにでも彼女を腕の中に閉じ込めることもできた。
けれど。
「頑張らなくていいんだよ。無理しなくたって、あんたはきっと、素敵な女性になれる。」
オリヴィエはそっと、ロザリアの耳元に唇を寄せた。
伝えたいことは、ただ一言。
それだけで、よかった。
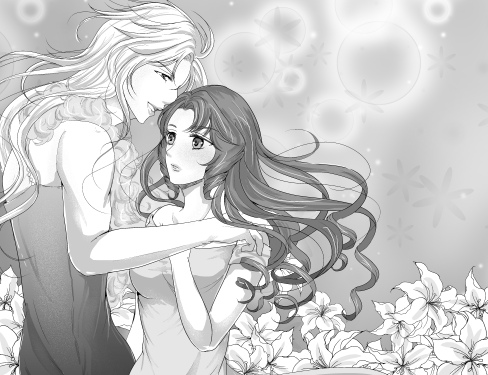
月の曜日。
校門をくぐったロザリアは、走り込んできたアンジェリークに早速飛びつかれた。
「ロザリア~~~。 宿題、見せて~~!!」
緑の瞳をウルウルさせて、すがるようにロザリアを見つめるアンジェリーク。
きっと彼女に尻尾があれば、ぶんぶんと振っているに違いない。
ロザリアはしがみついている腕を引きはがすと、わざとらしいため息をついた。
「仕方がない子ね! あの後、ちゃんとやっておきなさい、って言ったじゃないの!」
「だって~~~。 眠くなっちゃって昼寝したら、もう今日だったんだもん~~~。」
オリヴィエに送られて、アンジェリークの家につくと、深夜に関わらず、アンジェリークは起きていた。
気になって眠れなかった、と言われ、結局、朝までアンジェリークの質問攻めに付き合う羽目になったのだ。
とはいえ、ロザリアはその後、家に帰って、きちんと宿題も済ませたし、バイオリンの稽古もした。
ようするに心がけの違い、なのだろうけれど。
「ロザリア~~~。」
泣きつかれれば無下にはできない。
「教室に行ってからですわよ。 全く、あんたって子はどうして…。」
「えへ。」
ところがアンジェリークが笑った瞬間、金の頭にぱしんと硬いノートの縁が触れた。
「聞き捨てならないセリフだな。
堂々と宿題を写させてほしいとは、生徒会長が聞いてあきれるぜ。」
本当に呆れた顔をして背後に立っていたのは、たまたま今朝の生徒指導に当たっていたオスカーだ。
「アンジェリークは居残り決定。
ロザリアも犯罪に加担したから、同罪だ。」
「え! ロザリアは許してあげて~!」
「ダメだ! 他の生徒に示しがつかないだろうが。
二人は放課後、俺のところに来い。 嫌っていうほど説教してやる。」
「あーん!」
仕方がない、と、ロザリアは早々に諦めた。
とりえず、生徒会にも急ぎの仕事はないし、むしろこれでアンジェリークが真面目に宿題をしてくれるようになれば、ありがたいくらいだ。
「一緒に怒られてあげますわ。」
よしよしとアンジェリークの頭を撫でていると、オスカーの声が頭の上から降ってきた。
「また香水を変えたのか?」
どきん、とロザリアの鼓動が早くなる。
確かに香水を変えたが、まさか気づかれるとは思わなかったのだ。
すると、アンジェリークまでも
「ホントだ! 前よりもちょっと、甘い? でも、爽やかな感じもする?
薔薇…だよね? うーん、わかんないけど。」
くんくんと嗅ぎまくって、にっこりと笑った。
「ロザリアにすごくピッタリだね!」
「…ありがとう。 嬉しいわですわ。」
蕩けそうなロザリアの笑みに、オスカーは一瞬、心奪われた。
ついこの間までの彼女は、まるで硬い蕾だったのに、今の笑みは匂い立つ花のような美しさを醸し出している。
外見はどこも変わっていない。
そういうことには人一倍敏感なオスカーに気取られずにいられるほど、ロザリアは世慣れていないはずだ。
けれど、彼女の中ではなにかが変わったのだろう。
たとえば、大きな壁を乗り越えたような、そんな出来事があったのかもしれない。
いずれにしてもまだ、あきらめるつもりはないし、あの笑顔を見たら、あきらめられない。
「放課後だ。 ちゃんと来るんだぜ。」
教師と生徒なんてつまらない出会い方をしてしまった以上、せいぜい教師という立場を、有効に使っていくだけだ。
オスカーはロザリアにニヤリと不敵な笑みを向けると、校門前の指導へと戻って行った。
生徒が囲み始めたオスカーを残し、ロザリアはアンジェリークと連れ立って、歩き出した。
アンジェリークが鼻をくんくんさせては「いい匂い~。」 と繰り返しているのが、くすぐったくて、でも、とても嬉しい。
あの日の夜の別れ際、オリヴィエがプレゼントしてくれた香水。
「あんたがこぼした後から、私が作ったんだ。
あの香りも私は気に入ってるけど、今のあんたにはこっちの香りの方が似合うと思うからさ。」
ロザリアが作った精油をもとに、オリヴィエが調香した、世界にたった一つのロザリアのための香り。
それはあまりにも特別で嬉しかったけれど、もうあの部屋を訪れる口実が無くなったことは辛かった。
「もったいなくて、使えませんわ。」
ぎゅっと胸に小瓶を抱いて、ロザリアが言うと、
「無くなったら取りにおいで。
私は、たいていあの部屋にいるから。」
オリヴィエはダークブルーの目を細めてそう笑った。
小さすぎる瓶は、きっとすぐになくなってしまうだろう。
そのたびに会いに行ける。
香水は『いつでもあの部屋を訪れてもいい』という約束の印。
ロザリアは空を仰ぎ、特別棟に視線を向けた。
3階の窓にきらりと光る金の髪。
オリヴィエを見つける。
オリヴィエもまた、化学準備室の窓から、ロザリアの姿を見つけていた。
『待ってるよ。ずっと。』
あの時告げた約束は、この胸にずっとしまっておく。
今すぐ飛んでいくことは出来なくても。
未来はいつか必ずやってくるのだから。
Fin
