オリヴィエは遠ざかりかけたロザリアの後頭部に手を添え、ぐっと自分の方へと引き寄せた。
「まだ足りないよ。」
囁く吐息が彼女に届く前に、再び唇を重ねる。
あれだけのキスで足りるはずがない。
ここ最近、全く触れることができなかった分を取り返すには。
「ん。」
息をしようと開いたわずかな隙間から、舌を滑り込ませ、彼女のそれを絡めとる。
柔らかな舌は震えながらもオリヴィエを受け止めて、ぎこちなく彼女の熱を伝えてくれた。
舌先で顎裏をなぞり、絡ませ合っては吸い上げて。
彼女の口内を余すところなく侵していくと、逃げ場のない唾液がお互いの喉を伝っていく。
溢れていく水音を彼女に聞かせるように、わざと大きく響かせた。
ロザリアの膝ががくがくと震え、オリヴィエのストールにしがみついてくる。
「もう我慢できない。」
唇を触れ合わせたまま囁けば、ロザリアが小さく頷く。
オリヴィエはロザリアの膝裏に手を入れると、一気に抱き上げ、寝室へと向かった。
ベッドにロザリアを下ろすと、ストールを外し、丁寧に折りたたんだ。
それから、すぐ隣に座り、キスを再開する。
始めは唇をついばむような優しいキスを何度も繰り返して。
「くすぐったい。」
微笑むロザリアに笑みを返したオリヴィエは、彼女の髪に手を触れると、頭に乗っていたティアラをゆっくりと外した。
「これ、ゼフェルの手作り?」
繊細な細工の施されたツルバラのティアラは、とても素人の手作りには見えないほどよくできている。
サイドテーブルに置いてみると、葉っぱの一枚一枚までが手彫りされているのがわかった。
「ええ。 本当によくできていますわよね。 クレイシルバーというものなんですって。
さすが、器用さを司る鋼の守護聖ですわ。」
嬉しそうに言うロザリアに返事をせず、オリヴィエは彼女の髪に顔をうずめると、そこに何度もキスを落とした。
ふわふわと柔らかな髪がオリヴィエの頬をくすぐり、ロザリアの香りに酔いそうになる。
それから、オリヴィエはそっと彼女の手を取ると、指と指を絡めるようにして手を繋いだ。
「綺麗なレース。 ランディにしてはセンスがイイじゃない?」
オリヴィエの細い指がロザリアの手の甲を思わせぶりになぞっていく。
その触れ方が妙に艶めいていて、ロザリアの胸が高鳴る。
「オリヴィエ?」
両手を掴まれてしまったロザリアは、戸惑うようにオリヴィエを見つめる。
少し潤んだ青い瞳に、オリヴィエは微笑むと、ゆっくりと手袋を外して、彼女の指を口に含んだ。
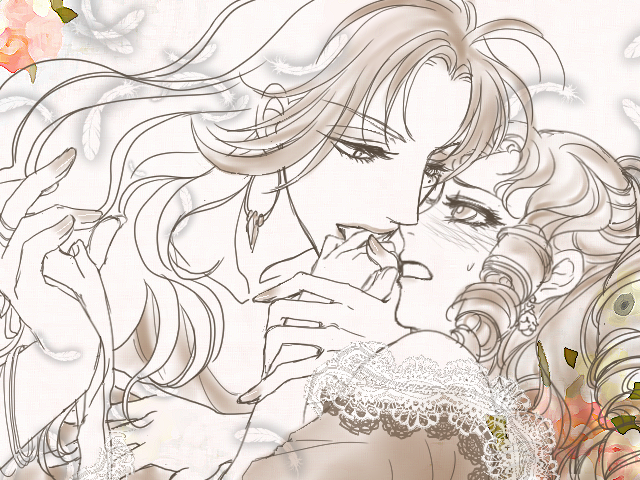
「え。」
ビックリして手を引っ込めようとするロザリアだったが、強い力に抑えられて抵抗できない。
オリヴィエはロザリアの指を一本、一本、丁寧に口に咥えていく。
上目づかいでロザリアから目を逸らさずに、時に舌先をのぞかせて舐め上げ、時には口の中で転がして。
そっと舌先で親指の腹を舐められ、びくりと身体が震えた。
「ん、ぁ。」
ロザリアは真っ赤になって必死で声を堪えていた。
指を舐められているだけで、身体の奥から、とろりと熱いものが流れ落ちてくるような感覚がする。
ただ指だけ、なのに。
はしたなく疼いてくる身体を、彼に知られることは、恥ずかし過ぎて耐えられない。
無意識に腿をすり合わせているロザリアに、オリヴィエは気づかないふりをして舐め続ける。
オリヴィエは10本の指を堪能した後、にっこりとロザリアに微笑むと、彼女の身体をベッドに押し倒した。
ふわんと柔らかなマットレスとブランケットに身体が沈み込む。
キュッと目を瞑り、オリヴィエの唇が降りてくるのを待っていたロザリアは、掴まれた足首に驚いて身を起こした。
慌てて、足元を見ると、オリヴィエが靴を脱がせている。
「ベッドで靴はいらないでしょ?」
両足の靴を床に落としたオリヴィエは、くすりと笑っている。
そして。
ストッキングをはいたままのロザリアの足の指を、いきなり口に含んだ。
「あ…。」
思いもよらない感覚にロザリアは声を漏らした。
ストッキング越しに柔らかなオリヴィエの舌が這いまわると、くすぐったいような、でももっと続けてほしいような不思議な気持ちになる。
手の時とはまた違う、もっとセクシャルな感覚。
それに体の刺激よりも何より、自分の足をオリヴィエが舐めているという事に、たまらなく背筋がゾクゾクした。
妖しく上目遣いでロザリアを見つめるダークブルーの瞳。
その視線に拘束されるように、ロザリアが動けずにいると。
「ストッキング越しじゃもどかしいね。」
オリヴィエは、言いながらも唾液をいっぱいに含んだ口でロザリアのつま先を出し入れする。
ねっとりと時間をかけて、ふやけてしまうほどに。
最後の小指がオリヴィエの口を離れた時、ロザリアはすでに頭がもうろうとしていた。
激しい快感を与えられたわけではないのに、心臓がどきどきして、身体の奥が熱い。
息を荒くして、マットレスに身体を預けているロザリアに覆いかぶさったオリヴィエは、優しく唇を重ね合わせた。
触れるだけなのに、すでに熱くなった身体には震えるほどに心地よい。
「ん。」
鎖骨をなぞるオリヴィエの手にロザリアが息を漏らすと、オリヴィエはそのまま手を首の後ろに回し、ネックレスの金具を外した。
「大きなタンザナイトだね。 あんたの瞳と髪の間くらいの色だし。 …すごくキレイ。」
チェーンを摘まみ上げて、光にかざすと、ロザリアの瞳よりも大きな宝石がキラキラと煌めく。
「ええ、セレスティアの宝石店で一番大きなものを選んで作らせたと…ぁ。」
いきなり胸元をキツく吸い上げられ、チリっとした痛みにロザリアが声をあげた。
拒む間もなく、ちょうどネックレスのあったあたりに、赤い花がいくつも散らされていく。
「あ、ダメですわ。 そこは・・・!」
補佐官服から見えてしまいそうな位置まで赤い花を落とされ、ロザリアはオリヴィエを軽くにらんだ。
「ふふ。 別に見えたってかまわないじゃないか。
あんたが私のモノだってこと、みんな知ってるんだから。」
オリヴィエの唇が鎖骨から胸のふくらみへと滑っていき、ドレスに触れる。
スクエアラインにカットされた上質のシルクのドレスは手触りも最高だ。
オリヴィエは身体のラインをなぞるように背中から腰、それから腿へと掌を這わせていく。
ドレスの裾をたくし上げて、足をゆっくりと撫でていくと、ロザリアの身体がびくりと震える。
ストッキング越しに与えられる、もどかしい快感に、頬を真っ赤にして指を噛み、声を堪えるロザリアの背に手を回して、オリヴィエはゆっくりとファスナーを下ろした。
背中からすっと外気が入り込み、思わずきゅっとロザリアの身体が縮む。
薄手のドレスとはいえ、脱いだ瞬間は多少の肌寒さを感じてしまうが、どうせすぐに熱に蕩かされてしまうのだから、寒気も一瞬のこと。
いつもならすぐに熱い愛撫が始まるのに、今、ドレスから腕を抜いたところで、オリヴィエの動きは止まっている。
なにかあったのか、と目を開いたロザリアは、自分の上にのしかかっているオリヴィエがじっと胸元を見つめているのに気が付いた。
「あ!」
大慌てで胸元を隠そうとしたロザリアの手を、オリヴィエが両脇でベッドに縫いとめる。
細身だけれどやはり男性のオリヴィエの力には構わず、ロザリアの身体は全く動かなくなった。
「や…。」
精一杯身体をよじり、なんとか視線を避けようとすると、オリヴィエは片手でロザリアの手首をまとめ直してしまう。
「ふうん。なるほどね。 これが陛下からのプレゼントってわけか。」
アイボリーのドレスの下から覗くのは、漆黒のレース。
オリヴィエは頭の上でロザリアの手首を抑えたまま、器用にドレスを足から抜いた。
純白のシーツの上に広がる青紫の髪。
その青紫に映える陶磁のように艶めいた白い肌。
そして。
ロザリアの見事な曲線を包む黒のランジェリーは一枚レースのブラとタンガ。
そして同じレースのあしらわれたガーターベルトとストッキングだ。
決して派手ではない、デザインとしてはむしろ定番ともいえるが、銀糸の縫い込まれたレースは、ほの暗い明かりの中でも輝きを放ち、レース越しに透けて見える素肌がなんともいえずエロティックな雰囲気を演出している。
フリルやリボンで飾り立てていない分、ロザリアの高貴な雰囲気を崩さずに、より官能的に魅せるランジェリー。
オリヴィエは知らずにごくりとつばを飲んだ。
「陛下の見立てはなかなかだね。」
かあっとロザリアの全身が熱を帯びる。
恥ずかしさのあまり、ぎゅっと唇をかんだロザリアの手の戒めを緩め、オリヴィエは彼女を抱き起こした。
「ね、この姿、誰かに見せたの?」
「いいえ! そんなはずありませんわ! ドレスに着替えるときに、アンジェに下着も何もかも持って行かれてしまって…。
仕方なくこれをつけたんですわ。
誰に見せるわけでもないと思いましたし…。」
着替えの時のロザリアの狼狽ぶりが思い浮かんで、オリヴィエはくっと笑いをこぼした。
そして、さぞかしアンジェリークは楽しんでいたことだろう。
「ねえ。立って見せて。」
「え?」
目を見開いたロザリアの耳元で囁く。
「もっとよく見たいんだ。 前も後ろも全部見たい。
この姿は私だけのものだって確かめさせて。 …せっかくの誕生日なんだからさ。」
ためらうロザリアの腕を引き、ベッド脇に立たせた。
恥じらうように身体を手で隠しながらもオリヴィエの言う通りに大人しく立っているロザリア。
誕生日だから多少のわがままなら許そうと思っているのだろう。
ほの暗いテーブルランプの明かりの中で見える彼女の身体は、すらりとしているのに、女性らしい曲線は完璧に整っている。
ガーターベルトの巻かれた折れそうなほどに細い腰。
その細い腰に不釣り合いなほど大きな胸はハーフカップのブラからこぼれおちそうだ。
きゅっと盛り上がったヒップを包むタンガは、薄いレースがかろうじて秘所を隠している。
身に着けているランジェリーのせいで、いつもなら清楚な立ち姿が、たまらなく妖艶で魅せられる。
オリヴィエはロザリアの背後に回ると、後ろからぎゅっと抱きしめた。
そして、そのまま彼女の顔を後ろへ向かせ、強引に唇を奪う。
「あ・・・ん。」
噛みつくような荒々しいキスに、ロザリアの口端から唾液があふれてくる。
口の中を舌でめちゃめちゃにかき回され、息もできないほどに蹂躙されて。
頭が真っ白になりかけたところで、オリヴィエがいつになく荒々しい手つきで胸を揉みしだきはじめた。
レースだけのブラは、オリヴィエの手にロザリアの柔らかさを存分に伝えてくる。
掌からはみ出すほどのボリュームを楽しみながら、オリヴィエは指先で胸の頂きを弾いた。
「ふふ、もうこんなに硬くしちゃって。 レースから飛び出しそうだよ。」
「や・・・。」
つんと硬くなった頂はレースを押し上げて、その存在を主張している。
オリヴィエはレース越しに頂を指でつまみ上げると、指の腹でこりこりと擦りあげた。
待ちかねた刺激に、ロザリアの全身に快感が走り、足が震えてくる。
甘い吐息で喘ぐロザリアに、オリヴィエはブラのレースを押しさげ、二つのふくらみを表に出すと、直に揉み始めた。
ブラで下から押し上げられたふくらみは、いつもよりも大きく盛りあがり、オリヴィエの掌に吸い付くように形を変えている。
オリヴィエは薄紅に染まった頂を親指と中指で摘まむと、人差し指で先端をひっかいた。
「はあん。」
背中を反らすと、耳のすぐ後ろにオリヴィエの吐息がかかり、耳からもぞくぞくするような快感を与えられる。
「こうされるの、好きだもんね。」
揉みながら先端を弄る。
指先で擦り、押し込んでは摘み上げて。
しばらく続けていると、ロザリアの腰が揺れ、膝が内向きに擦り合わされている。
必死で何かを耐えているロザリアの姿に、オリヴィエは片手をするりと内腿へと滑らせた。
滑らかな腿に掌を何度か往復させ、ショーツのクロッチに指が触れると。
「ふふ、すごい。 ここ、開いてるんだ。」
前から見た時はわからなかったが、ショーツのクロッチ部分は開いていて、そのまま秘所に触れられるようになっている。
オリヴィエが指をゆっくりと秘所に這わせると、すぐにぬるぬると蜜が絡みついてきた。
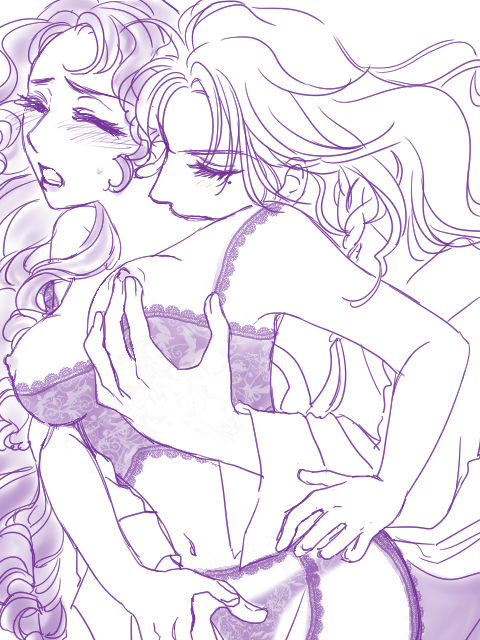
「もうこんなになってるよ。 すごい。」
蜜のついた指を見せつけると、ロザリアは顔を真っ赤にして俯いた。
実はもう指をくわえられているときから濡れていたのだが、恥ずかしくて、そんなことは言えるはずもない。
「そ、そんなことありませんわ…。」
否定しても無駄だと言わんばかりに、オリヴィエの指が蜜をすくい、滑らかに秘裂をなぞる。
「ねえ、いつから濡らしてたの? ホントはずっと感じてたんじゃないの?」
「や…違う、ん…。」
ぬるぬると指を動かせば、また蜜があふれてくる。
とっくにオリヴィエが気づいていたなど知らないロザリアは、いやいやと子供のように首を横に振っている。
補佐官の時は凛としていて、ジュリアスとでも対等に議論するロザリアなのに、夜の事になると途端に初心で無垢になるのだ。
苛めたくなるほどに可愛くて。
「いやらしい子だね、 ロザリアは。」
オリヴィエが囁くと、見てわかるほど、ロザリアの身体がかあっと朱に染まった。
「もっと悦くしてあげるからね。」
オリヴィエは指を花芯へと当てると、ゆるゆると撫で始めた。
中指を軽く埋め、浅いところをかき交ぜては、また滑らせて。
膨らんだ花芯をこすって、弾いて、摘まんで。
ロザリアの感じるところ全てを巡りながら触れていく。
「ああぁぁ・・・・。」
声にならない声がロザリアの口からこぼれた。
片手で胸を、片手で花芯を。
両方をオリヴィエの手で翻弄されて、ロザリアの意識は快感に支配されていく。
身体の奥から絶えず蜜があふれ、くちゅくちゅと淫らな水音を響かせる。
たまらない刺激に、止めてと叫び出したいのに、止まられたら狂ってしまいそうなほど、快感は強烈で。
花芯をこすられ続けたロザリアは、がくがくと足を震わせて達してしまった。
オリヴィエは前かがみに倒れそうになったロザリアを抱き上げて、テーブルのそばまで連れて行くと、そこに手をつくように促した。
支えを得て、テーブルにうつぶせに寄り掛かったロザリアが、息を吐こうとした瞬間。
「ごめん。 今日は優しくできないかも。」
オリヴィエはズボンの前を寛げると、すでに硬く立ち上がっていた昂りで、後ろから一気にロザリアを貫いた。
「や・・・!」
達したばかりの敏感な身体に強烈な快楽を与えられて、無意識に逃げようとするロザリアの腰をオリヴィエはしっかりとつかんで離さない。
それどころか、さらに自分の方へと引き寄せて、打ち付けるように深くロザリアのナカを抉る。
いつも狭く締め付けが強いけれど、後ろから挿れたことで、さらにそれが強くなるように感じられて、オリヴィエは快感を貪るように突き上げた。
「ぁんん・・・あ…。」
ロザリアからあがる、悲鳴のような嬌声。
実際、ロザリアの意識は強すぎる快感で、だんだんと遠のきかけていた。
オリヴィエが突きあげるたびに、頭の後ろがジンと痺れて、繋がっている部分から全身へと電流にも似た刺激が走る。
今までに感じたことのないような強烈な快感は、感覚的に恐怖に近い。
「あ、もう、や、ダメ…。」
逃げ出そうと身をよじると、それがオリヴィエにはさらに快感になるのか、一層突き上げが激しくなった。
身体のぶつかる音と粘度の高い水が絡み合う音。
オリヴィエの荒い息とロザリアの喘ぎ声。
部屋の中に、それだけしか聞こえない。
「ん、やっ…! あぁ…。」
ある個所を擦り上げた瞬間、ロザリアの背中が大きく反った。
二度目の絶頂は、一度目よりも身体の奥深くで感じたもので、全身ががくがくと震え、ナカの締め付けが一層きつくなる。
搾り取られそうになる自身を引き抜いたオリヴィエは、力が抜けてテーブルに伏せた彼女の身体を抱き上げ、ベッドへと下ろした。
ベッドに下ろされたロザリアは、もう自分で動くこともできないのか、力なく横たわっている。
潤んだ瞳と上気した頬が艶めかしく、少し開いたくちびるはキスをねだっているようだ。
オリヴィエはようやく自身の服をすべて脱ぎ捨てると、さっと唇を重ね、ロザリアの足を左右に開いた。
ショーツの隙間から覗いている蜜で濡れた秘所は、ひくひくと蠢いて、快楽を待っている。
オリヴィエは昂りをあてがうと、今度は正面からロザリアを貫いた。
あふれた蜜が淫らな音を立てて、昂りを中へと飲み込んでいく。
「ああっ。」
快感をにじませた声に、オリヴィエの熱が上がる。
ロザリアももっともっとと自分を欲しがっているのだ。
もっと深く、もっと強く。
彼女のナカが自分を奥へと引き込もうとしているのがわかる。
腰を動かしながら、彼女の顔をもっと近くで見たいと、身体を折り曲げて唇を寄せた。
キスを降らせて、また突き上げて。
いつもなら、強弱をつけて彼女の悦いところを探っていけるのに、今はもう獣のように動くことしかできない。
オリヴィエという人間はこの場から消え失せて、彼女を貪るだけのただの雄になりさがっている。
優しくないどころか、壊してしまいそうなほど、貪欲に。
もう喘ぐだけしかできないロザリアがオリヴィエに腕を伸ばしてきた。
空をきる手に置き場を与えようと、オリヴィエが肩を差し出すと、ロザリアがそっとその肩に指先を乗せてくる。
ぎゅっと伏せていた青紫の睫毛がゆっくりと上がり、青い瞳がオリヴィエを見つめる。
目の端に涙を浮かべながら、ロザリアは小さく微笑んだ。
「す、き。」
声にならない言葉をロザリアの唇が形作る。
もちろん音になって聞こえたはずはないのに、オリヴィエの耳にははっきりとその声が聞こえてきて。
身体の快楽を越えたところにある愛おしさに、オリヴィエは心臓がぎゅっとつかまれるような痛みを覚えた。
なによりも欲しかったもの。
彼女さえいれば、他には何もいらない。
『プレゼントはロザリアよ。』
…彼らはそれを知っていたのだろうか。
知られていたことを恥ずかしいと思うよりも、隠す必要がないことがたまらなく幸せだと思えた。
奥を突きあげた瞬間、ロザリアの身体が大きく跳ね、痙攣するようにひくひくとナカが蠢く。
ぎゅっと締め付けられ、オリヴィエもとうとう限界を超えてしまった。
「く…。」
腰をロザリアに押し付けるようにして、勢いよく吐き出される熱。
オリヴィエはそのまま、身体を倒し、ロザリアに口づけた。
「す、き、だ、よ。」
声には出さず、重ね合わせた唇を動かす。
ロザリアにはそれだけでも十分に伝わったのか、まだ整わない呼吸の中で、彼女は恥ずかしそうにほほ笑んでいた。
愛しいロザリアと心も体も重ね合わせて。
愛し愛されていることを確かめ合って。
それだけでバカみたいに幸せすぎて…どうしようもない。
軽くついばむようなキスを繰り返していると、まだ彼女のナカにあったオリヴィエ自身が、ふたたび硬くなってきた。
ゆるゆると腰を動かすと、ロザリアは
「あぁん! や、も、もう・・・。」
困ったように離れようとする。
そのロザリアの身体をオリヴィエはぐっと引き寄せて抱き起した。
繋がったまま、向かい合って座るような姿勢。
ロザリアもナカのオリヴィエの硬さをはっきりと意識したのか、戸惑った顔でオリヴィエの胸を押してくる。
オリヴィエはその手をやんわりと押しとどめて、くすりと笑みを浮かべた。
「せっかくのみんなからの気持ちのこもった誕生日プレゼントを、一度で満足しちゃ申し訳ないでしょ?
もっともっと何度だって、可愛がってあげなくちゃ、ね。」
「え?! …あん。」
あっという間に押し倒されたロザリアの抗議はオリヴィエのキスにかき消されてしまう。
そして再び始まった甘い愛撫に、すぐに抗議の気持ちすら忘れてしまって。
その後はオリヴィエの言葉通りに…空が白むころまで、二人は熱い時を過ごしたのだった。
翌朝。
目を覚ましたオリヴィエは、腕の中で眠っているロザリアの髪にそっと口づけた。
すっかり眠り込んでいる彼女は、まるで目を覚ます気配がない。
無理もないか、と、オリヴィエは苦笑した。
パーティの準備で疲れていたところに、あれだけ激しく抱いたのだ。
ロザリアは何度も達して、最後は倒れ込むように眠ってしまっていた。
ふと、オリヴィエの目にサイドテーブルに置かれた昨夜のプレゼントが映る。
ティアラと手袋とネックレス。
床にはドレスと靴とあのランジェリーも散らばっているはずだ。
たしかに昨夜の着飾った彼女はキレイだったけれど、その姿を見た瞬間、オリヴィエの胸はチリっと痛んだ。
彼女を美しくするのは、オリヴィエだけの特権のはず。
髪も手も足も体も…オリヴィエ以外の男を想わせるなにかが触れることが許せなかった。
彼らの痕跡を消そうとしたオリヴィエに、彼女は気づいていなかっただろうか。
子供じみた嫉妬。
申し訳ないけれど、この品物たちはオリヴィエのクローゼットの奥深くにしまっておくことになるだろう。
なにげなく手で髪を梳いていると、ロザリアがうっすらと目を開けた。
「あ、オリヴィエ…。 げほっ。」
ロザリアはかすれた声で、苦しそうに喉を抑えている。
「ふふ、昨夜、あれだけ啼いたからね。」
「な!」
頬を赤くしたロザリアは、ふたたび、ごほんと苦しそうに咳をした。
確かに二人ともパーティからなにも摂っておらず、喉がカラカラだ。
オリヴィエはするりとベッドから出ると、
「お水持ってくるから待ってて。」
軽くシャツを羽織り、キッチンへと向かった。
キッチンにはまだパーティの名残があったが、彼らはかなりきちんと片付けてくれたようだ。
食べ残しは冷蔵庫に入れてくれてあるし、ゴミの類も全部まとめてくれている。
これなら二人でやれば、残りはすぐに終わるだろう。
冷蔵庫からミネラルウォーターを取り出し、グラスへ注いでいたオリヴィエは、テーブルの上に小さな包みが置かれているのに気が付いた。
ただの紙袋かと手に取ってみると、小さなリボンが付いていて、『オリヴィエへ』と書いてある。
「これ、ルヴァの字?」
がさがさと音を立てて、袋を開けると、中に入っていたのは、カードと小さく折りたたまれた紙の包み。
包みを軽く振ってみると、なにやらカサカサと奇妙な音がする。
「なにこれ…。」
開けてみて驚いた。
中にあったのは、真っ黒な丸い塊で、不思議な匂いが漂っている。
「草…? 冗談じゃなくて臭い…。」
添えられていたカードを読んで、オリヴィエは目を丸くした。
『オリヴィエへ
私からの誕生日プレゼントは、とある惑星に四千年前から伝わるという秘薬です。
男性が飲めば、滋養強壮となり、一晩でサッカーチームができるほどの子宝に恵まれるそうです。
女性が飲めば、感度倍増、たちまち名器になり、一国の王もたぶらかすことができるとか。
二人のどちらが飲んでも、素晴らしい夜になること間違いなしです。
どうぞ使ってみてくださいね。
あとで感想を伺いますのでよろしくお願いします。』
「全く…人のことをモルモットにするつもりだね。」
オリヴィエはカードを袋の中にしまうと、袋ごとくしゃりと丸めてゴミ箱へ投げ入れた。
あのルヴァが見つけてきた薬なら、きっと恐ろしいほどの効果に違いないだろうが…。
そんなものがなくたって、十分熱くなれるのは、昨夜でもう証明済みだ。
オリヴィエはテーブルに残っていた包みもゴミ箱に入れようと投げかけて。
…思い直したように、包みを胸ポケットへと入れた。
「せっかくのプレゼントだし、もらっとこっかな。」
あっさり捨ててしまうには、ちょっと惜しい誘い文句。
すぐにではなくても、いつかは…試してみてもいいかもしれない。
初々しく恥ずかしがる姿も愛おしいが、淫らに乱れるロザリアも…一度くらいは見てみたいのが、男心というものだ。
あのランジェリーとこの薬だけは、クローゼットのちょっと手前に入れておこう、と考えるオリヴィエなのだった。
Fin
