少し飲みすぎたのかもしれない。
バルコニーでワイングラスを傾けていたジュリアスは、思わず手すりに手をかけた。
小さな波が砂を攫い、また海に帰っていく、引き潮のような感覚が足元を襲う。
グラスを落とさないようにふらつきながら部屋へ戻り、テーブルに置くと倒れ込むようにベッドへ体を預けた。
ジワリと上半身まで忍び寄る倦怠感に、ジュリアスは目を閉じる。
真っ先に浮かんだのは、彼女の顔。
考えなければならないことは、山のようにあるはずなのに、と苦笑しながらも、ジュリアスはあえて思考を変えようとは思わなかった。
彼女の笑顔、怒った顔、困った顔。
これだけの顔を、覚えているのならば、きっとこの先も生きていけるはずだ。
ジュリアスは波のように揺れる感覚の中で、いつの間にか眠りについていた。
次の日は昨日の星空がウソのような雨模様だった。
いつもよりも念入りにブラシをかけた執務服を着たジュリアスは、聖殿に上がると、真っ先に女王の間へ向かった。
女王と守護聖たちはすでに気づいているはずだ。
もとより隠すことなどできはしないのであれば、せめて自分の口から伝えたかった。
「陛下。お伝えしたいことがあります。」
女王は玉座から蒼い瞳をまっすぐに下ろし、ジュリアスを見つめている。
その瞳に憂いを感じるのは、自分の願望なのかもしれない、とジュリアスは思う。
彼女も同じ想いであればいい、自分との別れを惜しんでいてくれればいい。そう願っていたから。
「交代の時が訪れたようです。すぐに次代の守護聖をお探し下さい。」
「ええ。すでにサクリアの欠片が感知された場所に、研究院の者を派遣しておりますわ。…あなたは引き継ぎの準備にかかってくださいませ。なるべく執務はクラヴィスに代行させるように。」
冷静な女王の言葉にジュリアスは身を固くした。
当然の処置と思いながらも、足元の砂を攫う波が一段と大きくなるのを感じてしまう。
女王の間を出たジュリアスは、クラヴィスの部屋を訪れた。
彼は相変わらず長椅子に寝そべったまま、起きているのか寝ているのかもわからない様子でいたが、ジュリアスを見て、ほんの少し眉を上げた。
「用件はわかっているな?」
「…ああ。」
二人の間に流れた月日は、その言葉だけで全てを伝えるのに十分だ。
ジュリアスがトーガの裾をなおし、部屋を出ようとしたとき、壁を伝うろうそくの炎が揺らいだ。
思わず足をとめたジュリアスの背中にクラヴィスの声が降る。
「お前は私とは違うと思っていたがな…。」
ジュリアスはぐっと袖を握ると、大きく息を吐いた。
なにもかも、さらけ出してしまえば楽になれるのかもしれない。
愛する女性との永遠の別れを、彼も共有しているはずなのだから。
それでもジュリアスは何も言わず、そのまま足早に自らの執務室へと戻ったのだった。
メインの執務から外れると、思ったよりもずっと時間が空いてしまう。
ジュリアスは早々に執務室の片づけを終えてしまっていた。
もともと整理整頓されていて、いまさらやることは特になく、新守護聖に最初に渡す物や分類を書きとめたファイルなどをまとめておくだけだ。
幼少のころから過ごしてきたはずの部屋なのに、私物もほとんどない。
引き出しを一つづつ空にして行くつもりで、一番大きな引き出しを開け、中の物をすべて出すと、色の変わった包装紙があった。
「こんなところに…。」
淡いブルーの包装紙はほとんどが白く褪せている。
包みを開けたジュリアスは、まるで昨日のことのように、あの日のことを思い出していた。
女王試験も半ばを過ぎた頃、ジュリアスはロザリアをよく遠乗りに誘っていた。
乗馬は貴族のたしなみとして、二人とも慣れていたし、なによりも気晴らしには最高だった。
馬上から小高い丘の風の中、草の流れを見ていると、些細なことは忘れてしまう。
始めは思ったよりも繊細なロザリアの気晴らしのためにと誘っていたのだが、いつしか自分が強く望むようになっていた。
二人きりで過ごす時間を、かけがえのないものと思ってしまったから。
あの日も、ジュリアスが声をかけ、いつものように丘へ出かけた。
女王の力が後退していたせいなのか、飛空都市は天候が突然不順になることがあった。
それまで雲一つない晴天だったというのに、ロザリアが馬を下りた瞬間、髪が舞いあがるほどの突風が吹き、思わずよろめいた彼女の手の先に馬の腹が触れる。
敏感な個所に急に力を込められた馬は大きくいななくと、後ろ脚を思い切り振り上げた。
「あ!」
蹴られる、とロザリアが目を閉じた瞬間、彼女の身体が地面に倒された。
馬に蹴られたにしては軽い衝撃。
ただ、おどろいて動くことができないまま耳をすませば、ジュリアスが馬に声をかけているのが聞こえた。
「よい子だ。そなたは悪くない。だから静かにするがよい。」
腹をさすりながら、馬をあやすような声。
馬が足を上げた時、ジュリアスはとっさにロザリアを押しのけていた。
自分の危険よりも、彼女を守りたいと勝手に体が動いていたのだ。
馬も一度蹴りあげたことで落ち着いたのか、ジュリアスの言葉を聞いて、反省しているように鼻を鳴らしている。
ようやく起き上がったロザリアがジュリアスに近づくと、彼の近くの地面にぽたり、と深紅の雫が落ちた。
「ジュリアス様!お怪我を!」
言われてジュリアスは頬の痛みに気がついた。
彼女の無事がありがたくて、そんなことはどうでもいいとさえ思える。
けれど、ロザリアは真っ青になって、蒼い瞳に涙を浮かべた。
「申し訳ありません。」
身体を震わせて何度も頭を下げるロザリアの肩にジュリアスはそっと手を置いた。
「私がしたくてしたことだ。そなたが気に病む必要はない。」
「ですが…。」
動揺が彼女の殻を外してしまったのか、いつも大人びている姿が年相応の少女に見える。
抱きしめたいと思う気持ちを必死に抑えつけた。
「自分が傷を負うよりも、そなたが傷を負うほうが、私にとっては遥かに耐えがたいのだ。」
頭を下げたままだったロザリアが顔を上げ、ジュリアスを見つめている。
ほんのり染まった白い頬。
思わず言葉にしてしまった真意を彼女は気がついたのだろうか。
けれどロザリアはただ黙って、白いレースのハンカチをジュリアスの頬に当てた。
布越しに伝わる彼女の細い指の感触がジュリアスの鼓動を大きくする。
しばらくすると血は止まり、その後はいつものように遠乗りを楽しむことができた。
血をぬぐったハンカチには赤茶色の染みがついてしまい、そのまま返すことをためらったジュリアスは、新しいものを用意した。
しかし渡す前にロザリアは女王になってしまったのだ。
渡せなかったハンカチは伝えられなかった想いと同じように、引き出しの奥にしまわれたままで。
ジュリアスは包みとハンカチを両手で丸めると、ゴミ箱の中に投げ入れた。
これからの人生にもう、過去は必要ないのだから、と。
いままで多くの守護聖を送り出してきた自分が今度は送られる側になる。
神鳥と聖獣の両宇宙から仲間だけを呼んだささやかなパーティ。
ジュリアスは次々と挨拶に来る守護聖たちに、きちんと礼を返しながら、ロザリアの姿を眺めていた。
大広間のシャンデリアは、光にあらゆる角度を与え、彼女の上に虹色になって降り注ぐ。
聖地を去ることが決まってから、ロザリアと二人きりになることはなかった。
避けられていたのかもしれない、とも思う。
クラヴィスや他の守護聖たちと話しているのを何度か見かけたが、ジュリアスに気がつくと、目をそらすようにして離れていくのだ。
そのたびに胸が痛んだが、仕方がないのだと、どこかであきらめてもいた。
きっと今夜も当たり前の挨拶を当たり前に交わし、そして終るのだろう。
ならば少しでも、彼女の姿を瞳に焼き付けておきたい。
ジュリアスはボーイからグラスを受け取ると、彼女に向けて小さく掲げた。
「もう、あんたに怒られることもないのかと思うと寂しいね。」
背後からかかる声。
「さすがにそなたでもせいせいする、とは言いにくいのだな。」
軽口で返したジュリアスにオリヴィエは驚いたように目を丸くした。
「怒られると、かえって発奮するっていうのが私の悪い癖みたいでさ。しばらくオシャレもやる気が出ないかもね。」
「それは何よりだ。新しい光の守護聖はまだ幼いゆえ、そなたの趣味が伝染しないとも限らぬからな。」
くっとオリヴィエが吹きだした。
「いつもそういうふうに話してくれれば、あんたとももっと話せただろうにね。」
「そうかもしれぬな。」
女王の笑い声が耳に入って、ジュリアスはついそちらへ顔を向けてしまった。
自分ではわからないが、長い間見つめていたのかもしれない。
気がつくと、オリヴィエが見たこともないような優しい瞳をしていた。
「また、いろいろ話せると思うよ。」
オリヴィエは意味ありげにウインクをすると、グラスを取り、別の方へと歩いて行った。
ジュリアスが呼びとめようかと迷っていると、広間に流れていた音楽が変わり、明かりが一段階落とされる。
いよいよ終わりなのだ。
いつの間にかロザリアが前に立ち、スポットライトを浴びている。
彼女以外、目に入らない。いや、入れたくなかった。
それほどに、今日の彼女は美しい。
いつも前を向いている青い瞳が、今日は一段と輝きを増し、世界を圧倒するような光を放っているようにさえ見える。
女王ロザリアは渡されたマイクを握ると、にっこりと微笑んだ。
「本日は光の守護聖ジュリアスの退任パーティにお集まりいただき、ありがとうございます。」
皆の視線がさっとジュリアスに集まる。
視線に押されるようにして、前に出たジュリアスは女王の背後へ並んだ。
この後、最後の挨拶をして、パーティがお開きになる。
考えてきた挨拶の言葉をもう一度ざっと頭に並べ、ジュリアスは時を待った。
ロザリアの凛とした声が広間に響いている。
「最後になりますが、聖地の典範を変更しました。守護聖の皆には協力していただいたことを深く感謝します。」
クラヴィスが唇の端を上げるのが見えて、ジュリアスは驚く。
この場にいる自分以外の誰もが、なにかを共有している空気。
けれどもそれは不愉快なものではなく、どちらかというと暖かいものにすら感じられる。
考えているうちに、ロザリアが振り向いた。
「ジュリアス。」
不意に名前を呼ばれて面食らい、まともに返事が返せなかった。
「結婚すれば、サクリアがなくなっても聖地にとどまれるようになりましたの。女王も、守護聖も、聖地の者は一人の例外もなく。
この先ずっと、愛し合う者同士を引き裂くような愚かなことが、なくなるように。」
ゆっくりと一言一言をかみしめるような、彼女の言葉。
ジュリアスは理解すると同時に声を上げた。
「なぜ、そのようなことを? 慣例を破ることは陛下の治世に多大な影響を与えるはず。反発する者も多くなりましょう。」
実際、古きを貴ぶ者たちからすぐにでも抗議の声が上がるだろう。
女王陛下が、補佐官が、守護聖が、結婚する。
そんなことが許されるはずがないのだから。
「反発なんてものはどうにでもなりますわ。わたくしが女王なんですもの。」
「ですが。」
なおも言おうとするジュリアスをロザリアは微笑むことで制した。
「わたくしがしたくてしたことです。」
「今回のことで非難される事よりも、なにもせずに失う事の方が、遥かに恐ろしいと思いましたの。
これから未来の女王や補佐官や守護聖たち、皆が悲しむことが無くなれば、それが何よりだとは思いませんか?」
そこまで言って、ロザリアはほんの少し目をそらした。
耳まで朱に染まる頬。よく見れば細い肩が小刻みに揺れている。
ジュリアスの胸がざわめいた。
彼女が『なにもせずに失いたくないもの』。
未来の聖地のためという言葉もウソではないだろう。
だが、彼女自身の願いがあればこそだと、そう思ってしまうことはうぬぼれだろうか。
ジュリアスはそっとロザリアの手を取った。
そらされていた蒼い瞳がジュリアスをまっすぐに見つめる。
彼女が作ってくれた未来に、自分のしたいことは、ただ一つ。
「変更された典範を最初に利用したいと願う私をお許しください。陛下の夫として、聖地にとどまる栄誉を私に与えていただきたい。」
大広間がしんと静まり返った。
ジュリアスにとって長い時。
蒼い瞳を潤ませたロザリアが小さく頷くと、ワッと皆の歓声が上がった。
「よかったよ。走り回ったかいがあるってもんさ。」
「ええ、ええ。このことはぜひ、後世に伝えなければなりませんねえ。」
「ったくよ、イライラさせんなっつーの。」
「次はわたしの番なんだから!」
わらわらと駆け寄り、祝福の言葉を投げかける守護聖たちの向こうで、クラヴィスだけはその場にじっと立っている。
ジュリアスと視線がぶつかり、クラヴィスはなにかを掲げると、薄い笑いを浮かべた。
捨てたはずの色褪せた包み。
クラヴィスは驚いているジュリアスに近づいた。
「なぜ、そなたがこれを!」
「簡単に捨てられぬであろう…。」
この包みと一緒に捨てようとしていた彼女への想いに気づかれていたのだ。
吐息が漏れるような笑い声がして、クラヴィスの唇がゆっくりと言葉を形作る。
「お前は違う道を行くがよい…。」
ジュリアスは静かに頷いた。
想いを叶えることができたのは、ロザリアが未来を得ようとしたからだ。
愚かにも過去を捨てることしか、自分は考えていなかった。
もう離さないという想いを込めて、彼女の手を握ると、ロザリアは恥ずかしそうに、けれど花が咲くように微笑んだ。
「さあ、今から、婚約パーティに変更よ!」
補佐官アンジェリークの声で再び乾杯が始まる。
虹色のシャンデリアは、その夜、外が白むまで賑やかな笑い声を聞いたのだった。
Fin
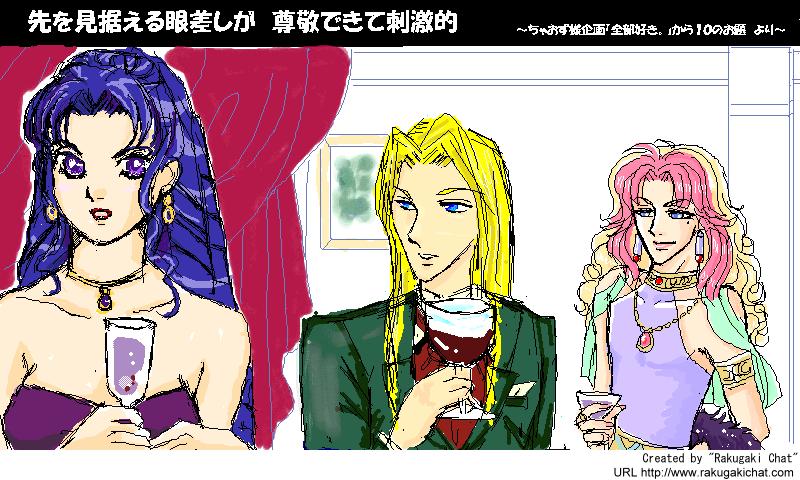
このお話はこちらのイラストからイメージして書かせていただきました。
ジュリ誕2011の絵チャログです。
ロザリア:ゆみこ様、 オリヴィエ様:しろがね様、 ジュリアス様:ちゃおず
「ジュリアス様の誕生日パーティでのひとコマ」というテーマだったのですが、お話を書くにあたり、設定を変えました。
ジュリ誕企画の中のイベントにもかかわらず、このお題からお絵描きしてくださった、ゆみこ様、しろがね様。
本当にありがとうございました。
