「君に出会えた今日は、俺にとっても幸せな一日になるぜ。」
「笑顔が眩しいな。」
次から次へと口から飛び出す美辞麗句。
ひやかした店にいる女性従業員達それぞれに逐一声をかけるマメさ。
このエネルギーをもっと宇宙のために有効に使えたら…。
隣で四方八方に愛想を振りまくオスカーに、リュミエールは小さくため息をついた。
ここはセレスティアの贈り物の園。
今日はオリヴィエの誕生日で、そのパーティが、女王と補佐官主導で開かれることになっている。
それ自体は毎年のことで珍しくもないのだが、今回はいつもとは違い、守護聖達それぞれにも仕事が与えられていた。
二人の仕事は、オリヴィエのための花を用意すること。
ロザリア曰く、
「オスカーなら女性へのプレゼントで、しょっちゅう花束を抱えていますから、今更恥ずかしくないでしょう?」
あの時の彼女は嫌味たっぷりなようにリュミエールには思えたが、オスカーは全く気が付かなかったらしい。
「そうだな。 俺ほど花の似合う男はいないからな。」
と、ご満悦だった。
幸せな男としか言いようがない。
そして、リュミエールはといえば…オスカーの監視役、と理解している。
「お花に詳しい方もご一緒したほうがいいですわね。」
その人選に関しては、さすが補佐官だ。
花といえばマルセルが一番だが、彼ではオスカーを抑えきれないだろう。
オスカーが本当の意味で苦手なのは、おそらくリュミエールだから。
ジャルダン・ナチュールは相変わらず、花の香りに満ちている。
リュミエールは香りに誘われるように、店内に足を踏み入れると、さまざまな花を見て回った。
オリヴィエは自他ともに認める、華やかな容姿の持ち主だ。
彼に似合う花、というのは、かなりハードルが高い。
リュミエールが真剣に考えているにもかかわらず、一方のオスカーは店員の女の子に話しかけてばかりいる。
「君みたいな美しい花がいたんじゃ、この店も商売あがったりだな。
花の美しさがかすんじまう。」
「まあ。」
「本当さ。 君という花の香りに酔ってしまいそうだ。」
ほんのりと頬を染める少女にオスカーがふっとほほ笑む。
二人の間に流れる甘い空気がリュミエールの方にまで流れてきて…。
リュミエールのこめかみがほんのわずかにぴくっと動いた。
「オスカー、先日の女性に贈った花はこれですか?
いえ、先週の女性ではありませんよ。 3日前の女性です。
たしか2週間前まで付き合っていた女性には、ピンクのバラを差し上げたと言っていましたよね。
ああ、その前の前でしたか? 次々代わるので、覚えきれなくてすみません。
でも、このひと月で5人とは、以前よりは長続きしてるようですね。」
にっこりとリュミエールが微笑みかけると、オスカーの頬が引きつる。
そして、今の今までとろけそうな瞳でオスカーを見つめていた少女も、ハッと目を覚ましたように、奥へと去っていってしまった。
「お前…。」
オスカーが苦虫を噛み潰したような顔でリュミエールを睨み付けてくる。
けれど、リュミエールはただにっこりとほほ笑み返していた。
「少しはまじめに選んでくださいね。 陛下たちも待っているのですから。」
リュミエールはオスカーから離れ、並べられた花に視線を向けた。
オリヴィエらしいピンクの大輪のバラもいい。
優雅なカサブランカやカラー。
カラフルやガーベラやチューリップも華やかで彼に似合うだろう。
どれかひとつに決めるのは難しい。
考え込んだリュミエールがふと視線をあげると、少し先の花の前でぼんやりしているオスカーの姿が目に入った。
いつも人を食ったような顔ばかりをして、傲慢で自信満々な炎の守護聖。
その彼の、少し寂しげな横顔が気になった。
「どうかしたんですか? スイートピーがなにか?」
近づきつつ尋ねると、オスカーはまだ花を見つめたまま、ふっと小さく笑った。
「いや…。 これがスイートピーなんて知らなかった。
ただ、誕生日なんだな、と、思っただけさ。
守護聖は年を取らないなんて言うが、ちゃんと誕生日は来るんだ。
俺たちが聖地に来てから、何度目になるのか…。」
その間に、故郷はどれほどの月日が流れたのか。
自分だけが残り、何もかもが失われていく。
掌から砂が零れるように。
「さあ、何度目でしょうね。 …もう数えていませんから。」
リュミエールの小さな嘘に、オスカーが気づかないはずはない。
けれど、オスカーは花から目を逸らさずに
「そうか。」
とだけ、つぶやいた。
「なあ、リュミエール。 オリヴィエといえば、お前、覚えてるか?
アイツが初めて聖地に来た日のこと。」
「ええ。 忘れるはずがありませんよ。
あのころのオリヴィエは荒んでいましたからね。
わたくしなど、随分な扱いをされました。」
「妙に冷めてたよな。 まあ、あの年になるまで、『普通』に暮らしてたんだ。
…なかなか馴染めなかったんだろう。」
「たまたま年が近いというだけで、よく一緒にされたものです。
ジュリアス様もオリヴィエには手を出しかねていましたから。」
「ああ、そうだったな。 ルヴァくらいか。 話してたのは。
ルヴァは良くも悪くも鈍いから、アイツの皮肉が通じなかったんだろう。」
「そうかもしれませんね。」
オスカーが語る思い出話にリュミエールも引きずられていた。
オリヴィエが来た日のこと。 自分が聖地に来た日のこと。 3人で当たった任務のこと。
少なからず、飲んだ夜。
語り始めれば、次々と話すことがあって。
積み重ねてきた日々の大きさに、改めて驚いた。
ふとオスカーが口をつぐみ、柔らかな風だけが花の中を通り過ぎる。
すると、二人の様子を遠巻きに伺っていた店員がおずおずと声をかけてきた。
「あの、お決まりでしたら、花束にいたしますけれど…。」
「ああ、申し訳ありません。 オスカー、どうしますか?」
結局何も決まっていないままなことに気が付いて、リュミエールが振り返ると、
「お前に任せる。」
呼び止める間もなく、オスカーは店の外へと出ていってしまった。
「全く…。 あの人は…。」
言いながらも、今日はいつものような憤りは感じない。
炎と水とは決して相いれないけれど。
強さと優しさはどこか通じているような気がした。
作ってもらった花束を受け取り、リュミエールが店を出ると、オスカーは空を眺めて立っていた。
「珍しいですね。 あなたが女性にも声をかけずに待っているだなんて。」
「ああ。 実は3人ほど声をかけたがフラれたんだ。」
「セレスティアの女性は見る目がありますね。」
嫌味の応酬も青空の下では、ただの軽口にしか聞こえない。
空は晴れていて、風は心地よく。
手にした花束からは甘い香りが流れてくる。
「紫のバラとはな。」
「オリヴィエにはピッタリでしょう?」
「まあな。 悪くない。」
青でも赤でもない、紫。
華やかな薔薇。
これ以上オリヴィエにふさわしい花はないと思った。
「あなたの誕生日にも、わたくしとオリヴィエで花を贈りますね。」
「いや。 俺の誕生日はレディたちに祝ってもらうことにしているからな。
むさくるしい野郎どもは遠慮しとくぜ。」
「陛下とロザリアにも同じ事をおっしゃれるのでしたら、喜んで身を引きますよ。」
「お前…。 本当に優しさの守護聖なのか?」
「残念ながら。」
にっこりとほほ笑んだリュミエールは、抱えていた花束の一つを、オスカーに手渡した。
「二つ? 一つでよかっただろう?」
受け取ったスイートピーの花束をオスカーは肩に乗せ、いぶかしげに眉を寄せている。
「一つはわたくし達からのプレゼントということにしませんか?」
「…べつにかまわんが…。 男が男に花を贈るってのはどうなんだ?」
「さあ、わたくしは悪くないと思いますよ。」
今までも、そして、これからも長い時を共に過ごす大切な友人のために、捧げる花。
スイートピーの花言葉は『優しい思い出』。
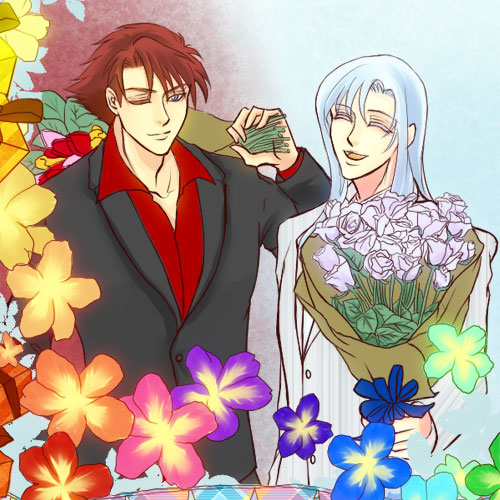
FIN
