Collaboration of B'z × Angelique
手の中のエルピス
『傷心』( 5th Mini Album「FRIENDS II」 収録 )
Illust by 美純様 Novel by ちゃおず
オリヴィエ×ディア、オリヴィエ×ロザリア
1.
「女王試験?」
「ええ。 次代の女王を決める大切な試験ですのよ。 私と現女王も受けましたわ。」
「ふーん。」
情事のあとのけだるい時間。
さらりと流された言葉に、一瞬、オリヴィエは理解が遅れた。
シーツからさらりと抜け出した彼女の背中を慌てて呼び止める。
「次代のって…。まさか?!」
「そうですわ。 …やっと、私もここを出ることができるのですのね。」
感慨深い長い溜息と懐かしむような笑みが彼女の顔に浮かぶ。
「なんとかして残れないの? あんたさえよければ…。」
結婚してもいい。
そう言いかけたオリヴィエに、目の前の女性は優しげな瞳を見開いて、すぐにくすくすと笑い始めた。
「いやですわ。 オリヴィエ。 まさかそんな…。」
彼女はすっと細い指をオリヴィエの髪に滑らせる。
「…あなたのこの髪が…。」
あの人と同じ色だったから。
彼がこの地を去った後、寂しさを紛らわせるために夜を共にしただけ。
なにげない、まるで明日の天気でも語るような口調で告げられた残酷な言葉が、オリヴィエの胸を射る。
「やっと彼のそばにいけるのですわ。 …ずいぶん遅くなってしまったけれど、待っていてくれているかしら。」
彼女のこんな笑顔は知らない。
こんな幸せそうで、こんな少女のような笑顔は。
オリヴィエは愚かな自分を心から嗤った。
愛されていると思っていた。 心から愛していたから。
「これからは忙しくなります。 …今日で終わりにしましょう。」
本当にそれだけで、彼女との時間は終わった。
それから間もなく、女王試験が始まった。
初めて謁見の間で二人の女王候補を見た瞬間、オリヴィエは神の悪戯、もっと悪く言えば陰険さに舌を巻いた。
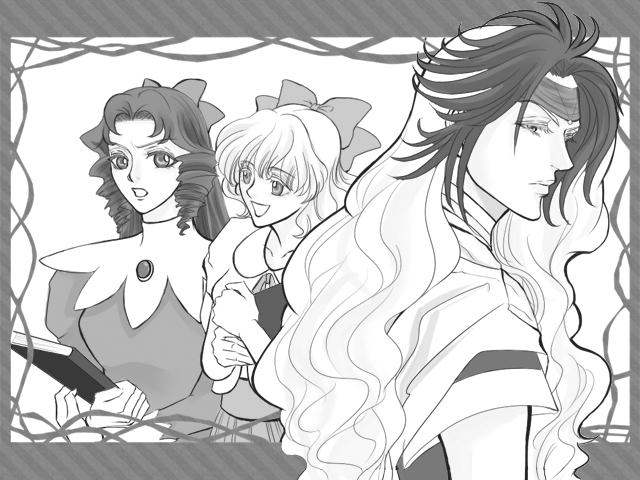
こうまで対照的な二人の少女を並べておいて、どちらかを選ぶ…。
当然のように守護聖達の間でも彼女たちへの関心はわかれている。
それはそうだろう。
どちらの少女もタイプだ、なんてことはあり得ないほど二人は違ってるのだから。
オリヴィエは当初から青い瞳の女王候補に興味を抱いた。
美しさをつかさどる彼としては当然のことかもしれない。
ロザリアの美しさはオリヴィエが今まで出会ってきた少女たちの中でも1、2を争う。
少し目がきついところはあるが、まさにパーフェクトといっていい容姿。
そして、どことなく彼女に似ている気がした。
目の色も髪の色も醸し出す雰囲気も、まるで違っているのに、ロザリアと彼女には同じ波長のようなものを感じるのだ。
女王試験が始まってからというもの、彼女は一段と忙しくなったらしい。
通常の業務に加えて試験があるのだから、当たり前だろう。
もっとも、たとえプライベートな時間があったところで、オリヴィエの事など思い出しもしないはずだ。
優しい微笑みの裏にある、無機質な瞳。
結局、彼女の中にオリヴィエは一部の必要性もなかったのだと改めて思わされた。
心にあいた大きな穴を埋めるように、オリヴィエはロザリアに積極的にかかわるようになった。
ロザリアはとても優秀で生真面目でなによりも純粋だったが、誤解されやすい部分も持っている。
そのせいでなかなか飛空都市になじめずにいたところを、オリヴィエが声をかけ、デートに誘い、とにかく彼女のそばにいたのだ。
オリヴィエがいれば、他の守護聖達もロザリアに声をかけやすい。
ロザリアも話しやすい。
そうしてオリヴィエはロザリアの心に入り込んだ。
得られなかった、彼女の代わりに。
「もうちょっと髪を切ったほうがいいんじゃない?」
青紫の髪を指で梳きながら、オリヴィエはロザリアの耳元に囁いた。
つややかな中にも柔らかさのある髪は強い癖のせいでオリヴィエの手の中でくるくると丸くなる。
本当に綺麗なロザリアの髪。
…でも、彼女の髪はもっと短いし、こんなに癖がない。
ロザリアは少し困ったように眉を寄せた。
「お父様が長い髪を気に入っているんですの。 …切ったら怒られてしまうかもしれませんわ。」
家族のことを思い出したのか、最後の方はくすくすと笑いだしそうなロザリアに、オリヴィエは「ふうん。」と、つまらなそうに髪を梳いていた手を止めた。
「私はその方が好きなんだけどね。」
オリヴィエが不機嫌そうに背を向けると、ロザリアは小さく息を飲んだ。
「ごめんなさい…。 オリヴィエが似合うというのなら、わたくし、髪を切りますわ。」
背中にそっと触れてきた手を邪険に払いのけ、オリヴィエは体を起こした。
同じシーツで感じていたぬくもりから急に放り出されて、ロザリアはおびえたように体を震わせている。
「いいよ。 別に。」
するりとベッドから抜け出したオリヴィエは、脱ぎ散らかされていた服を拾い集め、手早く身支度を整えた。
拒絶するようなオーラをまとう背中。
「ごめんなさい!」
慌てたロザリアはシーツを体に巻き付けたまま、オリヴィエに抱き付いた。
こんな時でも、ロザリアは淑女のたしなみを忘れない。
彼女と同じだと思うと、途端に気分がよくなった。
「怒らないで。 明日、あなたが切ってくださいませ。」
縋り付いてきたロザリアをオリヴィエは優しく抱きよせた。
「怒ってないよ。 …切らなくてもいいから。 あんたの長い髪、私だって気に入ってるんだよ。」
安堵した顔でじっとオリヴィエを見つめてくるロザリア。
オリヴィエを信じ、一心に愛する瞳だ。
…もしも、この瞳が彼女なら。
オリヴィエは彼女の唇を思い出しながら、ロザリアに激しい口づけを落とした。
「こんな…。」
オリヴィエの膝の上に乗せられたロザリアは、それだけ言うのが精一杯という風情で、うつむいた。
耳から首筋までが朱に染まり、唇をかみしめる姿。
可憐な薔薇が恥じらう様にオリヴィエの欲望が昂ってくる。
彼女との関係ではいつも自分を抑えてきた。
誰にも知られないように。 …彼女に嫌われないように。
けれど今は違う。
オリヴィエは背後からロザリアの耳を食むと、服の上からやわやわと胸を揉みしだいた。
だんだんと熱を帯びるロザリアの体。
オリヴィエはスカートの中に手を入れ、慣れた手つきで腿を撫でていく。
「…。」
真っ赤になって、じっと耐えているロザリアに、オリヴィエは手を奥へと進め、下着の上から刺激を与え続けた。
ぐっと握りしめられた手と耐え切れずにこぼれる甘い吐息が愛らしい。
しばらくしてショーツの横からするりと指を滑り込ませると、指先に熱い蜜が絡まる。
「いいよね…?」
オリヴィエが自身の昂りをロザリアの腿に押し付けると、彼女はふるふると首を横に振った。
お茶の時間の後、散歩をしようとオリヴィエから誘われて、この裏庭の外れまでやって来た。
聖殿のこんな奥までやって来たのはロザリアにとって初めてのこと。
ましてや東屋があるだなんて全く知らなかった。
背の高い草や野の花が植えられた裏庭は、薔薇や鮮やかな花たちに囲まれた中庭とは別の趣がある。
どこか穏やかで…寂しい。
オリヴィエに手を引かれ、東屋のベンチに二人で座った。
とたんに抱き寄せられて、深いキスが始まる。
けれど、いくら人気がないとはいえ、聖殿の一区画には違いない。
ロザリアはキスを受けながら、落ち着かずに、ついそわそわしてしまった。
「嫌なの?」
不意に唇が離れて、冷たい声が降ってくる。
ロザリアが驚いて目を開けると、オリヴィエが冷ややかな瞳で見下ろしていた。
「キスしてるのに、心ここにあらず、って感じじゃない? 嫌ならそういえばいいのに。」
怒らせてしまった。
ロザリアはつまらなそうに立ち上がったオリヴィエに震えてしまう。
普段の彼はとても優しいのに、時々こんな風にどうしたらいいのかわからなくなるのだ。
オリヴィエはロザリアの存在を無視したように、聖殿の一角を見つめている。
冷めたブルーグレーの瞳に、ロザリアはじわりとなにかに押しつぶされそうな恐ろしさを感じた。
ただ呆然としているだけのロザリアに、オリヴィエは再びベンチに腰を下ろすと、膝を指さした。
「ここにおいで。」
口調は優しいけれど、どこか有無を言わせない響きがある。
ロザリアは差されるまま、彼の膝の上にちょこんと腰を下ろした。
彼が笑みを浮かべたのが見えて、ホッとしたのもつかの間、オリヴィエはそのまま彼女の体を弄び始めたのだ。
指だけでロザリアが達してしまうと、オリヴィエは彼女の体を抱え上げ、東屋の壁に手をつかせた。
「自分だけイっちゃって…。 悪い子だね。
動いちゃダメだよ。」
スカートをまくり上げられたロザリアは、思わず振り返り、オリヴィエを見つめた。
彼のブルーグレーの瞳は、とても優しく見つめ返してくる。
いつもの彼。
まさかこんなところで、と思っていたら、彼が一気にロザリアに侵入してきた。

「!!!」
慌てて離れようとしたロザリアの腰をオリヴィエはがっちりとつかんで離さない。
「動いちゃダメ、って言ったでしょ?」
後ろから強く突き上げられ、体をゆすられる。
自分の口から出る甘い声と、繋がった個所からあふれる淫靡な水音。
耳を塞ぎたいくらいに、恥ずかしい。
ロザリアはせめて声だけでも、と唇をかみしめた。
それでも達したばかりの体はすぐに快楽を受け入れて、より深い快楽を連れてくる。
ギュッとロザリアが締め付けたのがわかって、オリヴィエも熱を開放した。
その場に崩れ落ちてしまいそうになったロザリアをオリヴィエは再びベンチに抱き上げる。
荒い息を吐くロザリアを腕に抱いたまま、オリヴィエはまたさっきの聖殿の一角を見つめた。
…彼女のいる部屋を。
オリヴィエは恋人になったロザリアを片時も離さないほどそばに置いていた。
育成のときも、もちろん夜も。
皆の前でも平気で甘い言葉をささやくオリヴィエに、ロザリアはとても恥ずかしがっていた。
怒ったり、時には拗ねたり。
でも二人のときは甘えてきたり。
夜だけの恋人だった彼女とは違う、ロザリアと過ごす些細な日常の日々。
初心なロザリアに淫らなことを教えていくのも純粋に楽しかった。
もしかすると、オリヴィエに夢中なロザリアを見せつけることで、彼女の関心を得たいという気持ちもあったのかもしれない。
傷ついてなどいない、と見せつけるつもりもあったのかもしれない。
けれど、次第にオリヴィエはロザリアに対してイライラした感情を持て余すようになった。
彼女と似ていると思ったのに、知れば知るほどロザリアは彼女とは違っているのだ。
「オリヴィエ、って言って。」
下で喘ぐロザリアの耳もとに囁くと、
「オリ、ヴィエ、さ、ま…。」
快楽で途切れがちになりながらも、ロザリアは精一杯の想いをこめて彼の名を呼ぶ。
「オリヴィエ、だよ。」
「オリ、ヴィ、エ…。」
オリヴィエにぎゅっとしがみついて、ロザリアが声をあげる。
「違うよ。 全然違う。」
彼女の声はもっと甘く、蠱惑的だった。
そんなにまっすぐで、オリヴィエだけを求めるような、切ない声じゃなかった。
オリヴィエはロザリアの口の中にそばに落ちていたスカーフを詰め込んだ。
そんな声は聴きたくない。
くぐもった声を上げるロザリアを、オリヴィエは欲望のままに突き上げた。
解放する熱と裏腹な暗い澱を心のどこかに感じながら。
彼女の瞳と色が違うから。
目隠しをしてみたり。
背を這う手の動きが彼女と違うから。
手をベッドに縛り付けてみたり。
そして、彼女ならきっと、柔らかい笑みで拒絶したであろうこと。
まだ明るいうちから執務室で抱くことも、口で奉仕させることも、オリヴィエが望めば、ロザリアは受け入れる。
けれど、懸命にオリヴィエの望みを叶えようとする姿を見れば見るほど、オリヴィエのイライラは増えていくような気がした。